1989~90年の日本株・土地バブル崩壊で日本は凋落したとお考えの方が多いですが、その後4~5年は「株や不動産に手を出した人たちが巨額損失を抱えこんだだけで、日本経済の根幹は健全だ」という見方が支配的でした。
1994年頃から「いわゆる日本的経営が間違っていたのであって、アメリカ式に刹那的利益を追い求める経営をまねるべきだ」といった議論が盛んになりました。ちょうどその頃、世界の製造業を牽引する国が、日本から中国に変わったわけです。
日本の製造業が世界を牽引していた頃、取扱総額だけではなく1件当たりの取扱額も上昇基調を維持していました。高級化・高品質化が進み、買い手も納得して高額化に応じ、先進諸国の生活水準が年々上がっていました。
ところが、製造業の主導権が中国に渡った頃から、世界貿易取扱総額は伸びていても1件当たり取扱額がどんどん下がっていく傾向が顕著になりました。「低品質でもいいから低価格の製品を」という風潮の蔓延です。
世界中の製造業が低品質・低価格志向になれば、設備投資やR&D投資もそれほど巨額の資金を必要としなくなります。
だから、21世紀に入ってからの経済危機の頻発も、2000~02年のハイテクバブル崩壊より、2001年に中国が世界貿易機関(WTO)に正式加盟し、ほんとうに必要な投資より利権団体にカネをばらまく口実としての投資が多くなったために起きたのではないでしょうか。
そうなると少しでも高い利回り・高い配当を求めて世界中をうろつくユーロダラーにとっても、次から次に危機の連発となります。
この連続危機の根底にあるのは、現在先進諸国では製造業の2~4倍の売上規模を持つサービス業が製造業ほど貿易になじまず、必然的に貿易総額の世界GDPに占めるシェアが低下していることです。
.png)
となると、冒頭でご紹介した日本経済の技術革新における優位も宝の持ち腐れとなってしまうのでしょうか? 私はそうは思いません。技術革新は決して製造業でしか起きないことではなく、サービス業でも不断におこなうべきことです。
ただ、サービス業の技術革新は製造業ほど莫大な資金を必要とせずにやれることが多いため「強きを助け、弱きをくじく」典型的な逆ロビン・フッド産業である金融業界の介在の余地が狭まります。
それは、一国の国民全体のためだけではなく、地球上の全人類のために健全な発展だと思います。
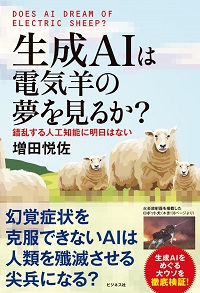 増田先生の新刊 生成AIは電気羊の夢を見るか? が好評発売中です。ぜひご覧ください。
増田先生の新刊 生成AIは電気羊の夢を見るか? が好評発売中です。ぜひご覧ください。
遊び道具としてならAIもおもしろく使えるが…… 米銀には10月こそいちばん残酷な月 生成AIの花形企業、エヌヴィディアに不正取引・粉飾決算疑惑浮上 開けてビックリ、好業績で割高さが再認識されたエヌヴィディア決算 アフリカ戦線異常あり 自動車自律走行はGREAT PIE IN THE SKY(バカでかい絵に描いた餅)
編集部より:この記事は増田悦佐氏のブログ「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」2023年11月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」をご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?










































