こんにちは。
さて、今日取り上げる話題は、バブル崩壊以降もう30年以上も低迷や停滞が続いてきたとされている日本経済を、先入観を排除して再考察することです。
そうすれば、日本経済が今もなおいかに強いか、そしてその強さがすなおに顕在化することを妨げているのは円安と超低金利だけなので、日本経済の復権はどんなに簡単かということを説明させていただきます。
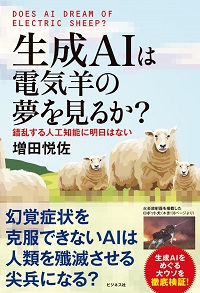

manassanant pamai/iStock
まず、次のグラフをご覧ください。
.png) いわゆる先進諸国と中国について、経済全体がどれほど技術革新に対して開放的かを示したグラフです。
いわゆる先進諸国と中国について、経済全体がどれほど技術革新に対して開放的かを示したグラフです。
2021年までは日本と韓国が首位争い、そしてアメリカとドイツが3位争いをしていたのですが、2022年に入って上位4ヵ国のうち3ヵ国で技術革新に対する開放度が下がり、ほんの少しだけでもさらに開放度が上がった日本の独走態勢に入りました。
2022年単年の変化で言えば、イギリスの開放度が急上昇しています。ですが、イギリスは国民経済全体が金融業界だけの片肺飛行のようになってしまった国ですので、おそらく金融技術の画期的な進展が見られただけであって、経済全体の開放度が上がったとは思えません。
実際に、製造業・サービス業・金融業・農林水産業など多種多様な業種にまたがる技術改革がたった1年でこれほど大きな成果をあげることは、ほぼあり得ないでしょう。
また、中国の場合、非常に低水準からとは言え、2021年まではかなり大幅な改善が見られていたのに2022年に悪化に転じて、ここで取り上げられている11ヵ国の中で最下位に戻ってしまいました。
次の2段組グラフの上段には、おそらく日本国民の大半がびっくりするような事実が表示されています。
.png) 2010年代半ばというと、バブル崩壊後25年も過ぎていて「日本経済はもう終わってしまった」といった悲観論ばかりが幅を利かせていた時期です。
2010年代半ばというと、バブル崩壊後25年も過ぎていて「日本経済はもう終わってしまった」といった悲観論ばかりが幅を利かせていた時期です。
そういった暗いイメージが定着してしまった日本の製造業付加価値に占める革新的な付加価値の比率は2015年から今年にいたるまで常に50%近辺を維持していて、日本、アメリカ、中国の3ヵ国プラスEUの4大経済圏の中で断トツの首位を維持していたのです。
なお、アメリカは製造業における革新的な付加価値の比率がずっとEUより低く、2020年には中国にも抜かれて最下位に転落したことも、意外と感ずる方が多いことと思います。
しかし、第二次世界大戦が終わったばかりの1946年に贈収賄合法化が実施されてからのアメリカ経済は、それまでのアメリカ経済とはまったく異質なものとなっていたのです。
業界を牛耳るガリバー型寡占の座を確保するまでは独創的なアイデアを連発していた企業が、ガリバーになってからは他社の技術革新を邪魔して無意味なモデルチェンジばかりするようになるのは、自動車業界のビッグスリーからアップルやマイクロソフトまで同一です。
さらに、下段には日本は世界の4大特許オフィスのうち3ヵ所以上で取得した特許件数の対GDP比率が突出して高いだけでなく、さらに増やしつづけていることがわかります。
2010年までは韓国がなんとか日本に追いすがろうとしていたのですが、どうやら2022年の段階では諦めてしまったようです。ドイツ、アメリカ、フランスといった欧米諸国中では比較的この比率が高かった国々も、やはり2022年の水準が2010年の水準を下回っています。
今後も技術革新における日本の優位は当分揺るがないでしょう。そして、次の2段組グラフを見ると、日本の首位が揺るがないだけではなくもっと2位以下との差を広げる可能性が高いとわかります。
.png) 上段を見ると、現時点での知的財産使用料収入では日本はドイツに次ぐ2位です。しかし、特許取得状況などから推察すると、ドイツはたまたま2010年以降急速に普及した技術の使用料収入が大きかっただけという可能性が高く、持続的に高水準を維持できるとは思えません。
上段を見ると、現時点での知的財産使用料収入では日本はドイツに次ぐ2位です。しかし、特許取得状況などから推察すると、ドイツはたまたま2010年以降急速に普及した技術の使用料収入が大きかっただけという可能性が高く、持続的に高水準を維持できるとは思えません。
また下段に眼を転ずると、知的財産権使用料支出では韓国、カナダ、日本がドイツを大きくリードしています。おそらくドイツの企業経営者には「自国の技術は世界最高」という思いこみが強く、他国の知的財産をカネを払って使わせてもらうことに抵抗があるのでしょう。
その点、日本の経営者はどこの国が開発した技術でも優秀な技術に使用料を払うことへの抵抗が少なく、全体として優れた技術の実用化に熱心に取り組んでいるのだろうと思います。というわけで日本は意欲的に技術を取り入れていますが、資金の取りこみには慎重です。
.png) 上段が諸外国から自国への直接投融資を受け入れている投融資残高でのトップ10ヵ国であり、下段は自国から諸外国への直接投融資支出残高でのトップ10ヵ国です。
上段が諸外国から自国への直接投融資を受け入れている投融資残高でのトップ10ヵ国であり、下段は自国から諸外国への直接投融資支出残高でのトップ10ヵ国です。
ほかの9ヵ国は投融資の受け入れにも拠出にも積極的な中で、日本は受け入れ側ではトップ10に入らず、アイルランドは拠出側でトップ10に入っていません。
「とにかく国際貿易や国際的な資本移動が多ければ多いほど良いことだ」と主張するグローバリストから見れば、日本は海外資金の受け入れについて閉鎖的過ぎるということになるのでしょう。
しかし、あとでくわしく検討しますが、現在日本は異常な円安政策を追求しています。
こういう状態で海外からの投融資を積極的に受け入れたら、モノやサービスばかりではなく、生産設備や蓄積してきた技術まで安く買いたたかれてしまうので、投融資受け入れに慎重なのスタンスは正解だと思います。
日本は世界最大の対外純資産国そのため、日本から海外への投融資残高は第7位とそれほど大きくないのですが、海外から受け入れている投融資残高がトップ10にも入らないほど少ないので、日本は世界最大の対外純資産国となっています。
.png)
日本から海外への投融資残高から海外から日本への投融資残高を引いた数字である、対外純資産が世界最大だということです。そして、黒字に白抜きの文章にもあるとおり、対外純資産は過去に積み上げてきた経常黒字の累計にほぼ等しいとされています。
最近の日本経済は貿易収支だけを見ると赤字になることも多いのですが、潤沢な対外純資産が稼いでくれる金利・配当収入が日本が諸外国からの投融資に支払っている金利・配当に比べてずっと大きいので、金融所得勘定で安定した黒字を維持しています。
さらに、諸外国からも「現在の円が異常に割安であって、これ以上円安が進むよりはむしろ円高に転換する可能性が高い」と見られていることは次の2段組グラフにも表れています。
.png)
国際貿易での決済通貨としては、一時は40%に達していたユーロのシェアが22%に激減し、その穴を48%とほぼすべての取引に関与している米ドル、7%台の英ポンド、ともに3%台半ばの日本円、人民元で埋めたかっこうになっています。
ところが、外貨準備としてどんな通貨を選ぶかというと、英ポンドは取るに足らないシェアに転落し、2019年まではほぼ日本円と同じシェアがあった人民元の2%に対して日本円は4~5%と差を広げています。
外貨準備、つまりいざというとき安定した価値を発揮するであろう通貨としては、日本円のシェアは安定しているのに、英ポンドや人民元には価値の保全に関して不安がつきまとっているわけです。
なぜこんなに円安が進んだのか?それにしても、なぜ21世紀初頭には1ドル107円だったものが、直近では1ドル約150円と、大きく円安・ドル高が進んでしまったのでしょうか?
たとえば、1980年代半ばに日本円は1ドル250円というかなりの低水準から1ドル150円への大幅な円高を招き寄せることに成功しました。円の為替レートが高くなるのは、それだけ諸外国から多くのモノやサービスが買えるわけですから、全国民の利益です。
そして、当時の外国為替市場は国内で物価が安定していて自国通貨の価値がしっかり保たれている国の通貨が高くなり、インフレで自国通貨の価値が目減りしている国の通貨が安くなるという、まっとうな経済論理の通用する世界でした。
.png)
上段を見ると、1980年代に日本円は主要通貨の中でいちばん水平に近いなだらかな下げ方になっていて、それだけインフレ率が低かったことがわかります。そして、下段には1985~86年頃に1ドル250円から150円へと大幅に円高が進んだことも確認できます。
この当時、米ドルはまだ当時の連邦準備制度理事会(Fed)議長ボルカーの「インフレ退治」と称する高金利の余韻が残っていて、金利は日本よりそうとう高かったのです。
しかし、金利の高さに引きずられて世界中からドル買いに資金が集中してドル高に進むことはなく、インフレ率が高く価値毀損も進んでいるドルは下がっていたのです。
豊かな国民生活を維持するには通貨価値の安定は欠かせませんから、インフレ率の低い国ほど自国通貨の為替レートが上がり、インフレ率の高い国ほど自国通貨の為替レートは下がって当然です。
次のグラフを見ると、日本の中央銀行である日銀の政府に対する独立性は低く、政府が無駄な財政投融資などで増やした借金の元利返済負担をインフレで目減りさせようとすることへの抵抗はあまり強くありませんでした。
.png)
それでも主要先進国の中でインフレ率をもっとも低く抑えられたのは、第二次世界大戦直後のインフレでひどい目に遭った日本国民が、インフレに対して非常に強い警戒心を持ちつづけていたからです。
その結果、日本円の価値はよく保全され、諸外国通貨に対して円高が進むことによって、日本国民全員が同じ円所得でも以前よりずっと多くのモノやサービスを諸外国から買うことができるようになって、急速な生活水準の向上が達成できたのです。
最近では、こうしたまっとうな経済論理に従って為替相場が動くことはなくなってしまいました。
インフレ率の高い国で「それでも国債を買ってもらわなければ財政が破綻するから」と無理やり高金利にした国債を乱発している国の通貨が目先の利益狙いで上昇し、インフレ率が安定して低いので国債も高金利にしなくても済む国の通貨が下落するようになっています。
「円安で製造業復活」はウソ国民を窮乏化させる円安が正しい政策だと主張する人たちの言い分は決まり切っています。「中国などの低賃金で低価格商品を量産できる新興国の台頭で、日本の製造業は危機に瀕している。だから円安にして日本の製造業の価格競争力を高める必要がある」に尽きます。
ところが、この主張は始めから終わりまでウソの塊なのです。まず、日本の製造業は新興国の低価格商品と直接競合しません。はるかに品質競争力が高いからです。
さらに、円安で製造業の利益が拡大するためには、少なくとも単価が低くなった分を補って余りある売上数量の増加がなければなりません。ところが、次のグラフでご覧いただけるように、円安には売上数量拡大効果はほとんどなかったのです。
.png)
日本の輸出業者は、始めのうち円建ての輸出価格をほぼ横ばいに保ち、輸出先での現地通貨価格を値引きしていました。2020年一杯がその時期です。
そうすると、第1次コロナ騒動での世界的な経済活動停滞があったこともあって、輸出数量は激減し、当然輸出総額も数量の減少と並行して大幅に減少していたのです。
日本の製造業が本格的に復活しはじめたのは、2021年の春以降、円建て輸出価格を円安分より大幅に引き上げて、輸出先現地価格でも値上げになるようにしてからのことです。
ここで重要なのは、輸出総額の激増の大部分は勤労者の賃金給与の増加ではなく、企業利益の増加に吸収されてしまうことです。
賃金給与だけではなく、下請けから調達した部品なども円価格で支払うことで「円安の恩恵」にあずかりながら、輸出先での販売価格は現地通貨ベースでさえやや値上げ気味になり、おまけにその売上を円に転換すると円安で見かけ上の増益幅がさらに膨らむからです。
こうして、輸出主導型の製造業各社の大半が「円安にしなければ価格競争力を失う」からではなく、彼らが楽して儲けるために円安推進論者となっています。 実際に2010年代の労働生産性の推移や設備投資動向を見ると、いかに製造業各社が設備投資もろくにしないで労働生産性を向上させていたか、それに対して設備投資を拡大していたサービス業各社は、ほとんど労働生産性を改善できなかったかがはっきりと出ています。
.png)










































