で!!!!!
重要なことは、
日本には、テスラのようなエリート主義じゃない、”現場の力”があるのだ!だから心配いらないのだ!だって”キズナ”があるからぁ!!!
…みたいなレベルの話をしたいのではないんですよ。
そんな、日本刀にこだわりまくって銃撃されて死ぬ侍みたいなロマンの話をしたいのではない。
「テスラ型の合理性」が黒船として攻めてきている以上、「その脅威」は決して過小評価せずにちゃんと相対して対処しなくてはいけない。
ただ、
「米国企業の一番良い部分」は、まわりまわって「社会の末端がメチャクチャなスラムに飲み込まれる事を許容する」という犠牲を払った上で成り立っている
…というこの因果関係をちゃんと理解することは、日本社会にも「米国企業型の合理性」をなんらか導入していきたいと考える時には必須なことなんですよね。
グローバルに透明性の高いロジックだけで出来上がった「水」の世界と、ローカルの特殊性に粘りつくように成立している「アブラ」の世界を、ちゃんと溶け合わせる、あるいはせめて「棲み分け」させる方策について考えないと、日本社会は最後まで「テスラ型の合理性の攻撃」に敗け続けてしまうことになる。
一方で、「ローカル側にあるアブラの世界の優位性」を決して壊されることなく、「水の世界の合理性」とちゃんと両立させる方法を生み出すことができれば、
「米国的な理想のあり方」が今まさに”世界の半分”から全拒否にされつつある現代人類社会の、『次のスタンダード的希望』
を、日本が生み出していくことも可能になる。
私はこれを、「2つのベタな正義」をどちらも否定しない「メタ正義」的な社会運営のあり方というように呼んでいます。
だからこそ、
・”グローバルな共通性”を徹底的に押し込んで来るテスラ ・”ローカルの特殊性”を徹底的に育て上げるクックマート
この2つの世界観を冷静に等価なものとして並べた上で、日本社会に「テスラ型合理性」に対抗できるだけの「合理性」が縦横無尽に通用するように持っていく事を考える必要が、これからの時代にはあるわけですね。
そんな感じでこの「後編」では、とりあえず「クックマート行ってみたらマジすごかった」っていう話から、白井氏の本からその「経営のあり方」みたいな話を引き出すと同時に、そこから「今後の日本社会の運営のあり方」「分断されゆく人類社会への日本ならではの新しい希望の提示の仕方」みたいな話ができればと思います。
ちなみに、今回記事、いきなり「クックマート公式」アカウントさんに発見されて好意的な反応をいただけました。その後、白井社長とも無事コンタクトが取れて、近々お会いできることになってめっちゃ楽しみです。
1. クックマートのどこが凄いのか(店舗行ってみた話)するど過ぎる洞察、恐れ入ります。テスラとクックマートを比較するという視点に恐れ入ると同時に、本質を見事に掴んで表現してくださっているところに驚きです。一企業の話を超えたこれからの社会につながる部分のお話も共感です。誠にありがとうございます。 Pc7Y0mCA
— クックマガジン by クックマート【公式】 (@COOKMAGAZINE_jp) September 2, 2023
さて、豊橋と浜松出身の人に聞いたら「クックマート?もちろん知ってるよ!」って感じみたいなんですが、他地域の人は普通知らないですよね。
でも、「食品スーパー」みたいに大して違いがなさそうな業態で「普通の倍」売るとかマジで想像できないな…と思って店舗に行ってみたんですけど、なんか確かに超凄いです。
まず、道路からクルマがずううううっと入ってきてるんですよ。客が途切れない。結構遠くから来てる人もいるんだろうなあ、という感じで。
で、お惣菜とか、カットフルーツとか、フルーツサンドとか、ベーカリーとかのクオリティが異常に高い。
「これを理由にここ選ぼう」って思うレベルだというか、家とか職場の最寄りスーパーがコレだったらQOL爆上がりするだろうな!って感じがする。
グルメなだけじゃなく値段も手頃で、満足感がめっちゃあるんですよね。



「クックマートは自社の従業員がお惣菜を必ず買って帰る」って聞いたんですけど、それぐらい「ちゃんと満足度が高いメニュー」が用意されている。
全体的に値段がめっちゃ安いって感じではないんですね。
むしろ「徹底した安売り専門」みたいなスーパーと比べるとどれもほんのちょっと高いぐらいの値付けだと思います。
「お値打ち」だが「激安」ではないというゾーン。
ただ、アイスボックス持ってって、普段の「今週の食料品」買い込むのをクックマートでやってみたんですが、当初は
・肉とか野菜とか=まあ普通に良い ・お惣菜とかその他=”ここに来るだけの理由”があるお値打ち品が揃っている
…ていう感じなのかな?って思ったんですが、今週買ってきた野菜使ったらめっっちゃ美味しくてびっくりしました。
玉ねぎはまあ普通でしたけど、人参とか水菜とかピッカピカのシャッキシャキで、同じ料理をしてても別ものみたいだった。
「水菜」は茨城県産って書いてあったので、別に地場の野菜にコネがあって新鮮なのを入れられてるって感じじゃあないと思うのですが、「こんなに違いが出せる」って理由はよくわからないけど凄いなと思いました。
ただ「仮説」として聞いてほしいんですが、食品スーパーって一年通して同じ店に行ってると、季節の移り変わりとともに野菜の品質ってかなり上下するなと感じるんですよね。
ある時期は「凄い美味しい野菜」を売ってる店でも、季節の移り変わりと同時にその「高いクオリティ」を維持し続けるのは難しい場合が多そう。
多分、同じ産地でも、「この時期」には凄い良いけどハズレな時期も出てくるから適宜移り変わり続けないといけないよね・・・みたいな必要性が常にある商品だから、
常にコチョコチョコチョコチョ微調整をし続ける事が必要な商品特性
↑こういう特性の商品は、「経営が中央集権的」だとうまく対応できない例が多い・・・というのは、経営コンサルタント的に「一般論」としては言えることではあります。
「目玉商品」的なお惣菜も、いわゆる「ザクザクのカレーパン」「●●産牛乳をふんだんに使ったソフトクリーム」とか、とかなんかそういう「一品だけ」のものを全面展開するのは「中央集権」的にできるんですよね。
でも、ある程度の「飽きが来ないバラエティ」のものを、季節によって千変万化するコスト構造に応じて微妙に変化させつつ「お値打ち感」を維持しながら展開し続ける…というのは別次元の難しさがある。
そのためには、まさに
常にコチョコチョコチョコチョ微調整をし続ける事が必要な商品特性
…が生まれるので、「クックマート型の経営の優位性」を出せる部分が出てくるんだろうなと。
こういう「工夫を吸い上げる」ってよく言われてるけど、でもこういうのちゃんと「戦略」側が知性的に仕切って「やる意味があるところ」でやらないと意味がないからね。
日本では「あまりやる意味ないところ」で「従業員に無理やり工夫を出させる」ことで疲弊している例もかなり多いので、この「知性」と「現場」が両輪で回っている感じが、やはり大事なところなんですよね。
全体的に、クックマートは
・まず最低限食品スーパーとして不満なところはない。どの分野でも常に80点ぐらいは取れる安定感 ・その上で、何気ない野菜や肉なんかも、結構高い確率で「大当たり」的なクオリティのものがある。 ・「目玉」としてのお惣菜関連の「来てよかった120点のキラーコンテンツ」がバラエティ豊かにある。 ・なんとなく従業員が楽しく働いてそうで、空気感が悪くない。店の感じが幸福感ある。
…みたいな感じだと思いました。
あとね、何かモノを訪ねたりレジの時とかの従業員さんの感じが、もちろん丁寧ではあるけど、やたら慇懃無礼で卑屈なほど腰が低いみたいな感じじゃないところが凄い良かったです。
これはほんと、日本の小売業の変わって行ってほしいポイントだと自分は思っていて、「卑屈に腰低い」はいいから、「当たり前の丁寧さ」にチューニングしていってほしいなと思ってるんですよね。
で、「お客様とて許せぬby湯婆婆」みたいなのは適宜ちゃんと言う方向に持って行ってほしい。
経営者側が思考停止して、「その店の売り」をちゃんと作り込めていないと、従業員に卑屈にペコペコさせるという「価値」を売り始めちゃうみたいなところがあるのかなと。
クックマートみたいに、「明らかにここに来る理由」を構造的に作れていれば、むしろ「当たり前の丁寧さ」ぐらいがあれば十分ですよね、という空間になるし、それが売り場の雰囲気を良い感じにしてるところがあると思います。
あと、単に「照明」のつけかたに工夫があるだけかもしれないけど、でも店内の感じは凄いホンワカ明るい幸せ感があって、その点もめっちゃ良かったです。
2. クックマートの「経営面」における工夫はどういうものか?さて、ここまで「クックマートの店舗に行ってみたらすごかった」っていう話をしてきましたが、次は白井社長の本を読みながら、その「すごさ」はどういう風に成立しているのか?みたいな話をしたいと思います。
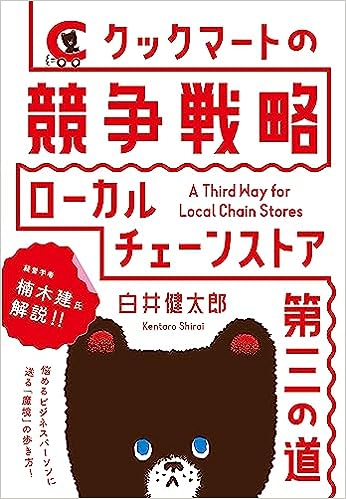
『クックマートの競争戦略 ローカルチェーンストア第三の道』
全体として白井社長は、「ロジック」的なものと、「その会社が持つ本来的な特性」みたいなものを、ちゃんとすり合わせて一個ずつ打ち手を打って行くタイプの人だと思いました。
いわゆる他社がやってる「ベストプラクティス」みたいな正解(とされるもの)があっても、簡単に考えなしにそのまま取り入れたりはしない。
例えば「チラシ」は出さないそうで、チラシは本部が「売りたいもの」を決めてしまって現場レベルで考える部分を奪ってしまうからやらない…という方針だそうです。
とはいえ、だからといって「その会社の昔からの惰性」をそのまま放置してるかというとそういうわけではなくて、かなり徹底的な対話的コミュニケーションの中から、「工夫を引き出してどんどん刷新していく」みたいな事が全社的に常に起きるように持って行っている。
テスラとの比較みたいな話で言えば、
「水の世界側の論理」
をある程度導入していきつつ、それを無理押しに現場に受け入れさせるというよりも、そこで
「アブラの世界の人々」
との”双方向コミュニケーション”を重視して、彼らの創意工夫を引き出しているという感じでしょうか。
白井社長はこの「アブラの世界の自律性」のことを
『魔境』
と呼んでいて(笑)、「魔境」には「魔境」なりの合理性や人々の気持ちがあるので、それを「一般的な理屈」だけで押し切ってしまわないようにしているという話が何度も出てきます。
白井社長個人はまあまあインテリで、東京の企業で働いてきた経験がある人なので、「基本的には水の世界の住人」だと思うんですね。
でも「アブラの世界」には「アブラの世界」の自律性があって、それがそうなっている『意味』も必ずある事を理解した上で、「対等な異文化」としてコミュニケーションする姿勢があるのが、こういう経営が「普通の倍」レベルの成果を上げている原因だと思います。
白井社長の本を読んでいると、この「魔境の独自性」をちゃんと尊重しつつ、お互い言いたいことを言い合えるようにしていくという態度を重視してる感じがありました。
「水の世界の論理」をゴリ押しして現場を壊すこともしないが、時代に合わない「アブラの世界の惰性」をそのまま放置したりも絶対しないという感じ。
定期的に従業員アンケートを取ってあらゆる不満を吸い上げるけど、「単なるわがまま」的なのはある意味「適切に無視」しながら、「真っ当な意見」はどんどん取り入れていって、「理不尽なこと」が現場に残らないように常に気をつけているという感じ。
要するに、「水の世界」と「アブラの世界」の間に、本当の意味での「違いを活かす双方向コミュニケーション」が実現できているところが、クックマートの強みなのだと言えると思います。
こういう「双方向コミュニケーション」があるので、さっき書いた
常にコチョコチョコチョコチョ微調整をし続ける事が必要な商品特性
を「乗りこなす」強みが他社を引き離す優位性になってるんですね。
なんかこう、
常にコチョコチョコチョコチョ微調整をし続ける事が必要な商品特性
こういう部分↑は、すべて「定式化」して「不確実性を排除」するのが、ある意味で「良い経営」だと思われてるところがあるんですが、それはちょっと一面的な見方でしかないんですね。
勿論、「いちいち不確実性に対処する意味がない」ような事象に毎回かかわずらって疲弊している…みたいなのは最悪で、経営とはそういう部分を標準化して無駄を減らしていくことが重要なのは言うまでもないのですが。










































