
クックマート 本野町店クックマートHPより
前編は、だいたい「テスラ車って乗ってみたらマジで凄かった」っていう話から始まって、その背後にある経営側面の特徴はどういうものか?とか、それに対して日本車勢はどうやって対抗していけばいいのか?、みたいな話をしています。
(前回:テスラ車が描く未来 vs. 売上日本一のローカルスーパーの世界観(前編))
で!後編では、(前半部分でも導入しておいたんですが)、「クックマート」というローカルスーパーの話をしたいんですよ。
クックマートは、豊橋と浜松にしかないんですが、なんと「一般的なスーパーの一店舗あたり売上の”倍”も売り上げる化け物スーパー」なんですね。
食品スーパーなんて素人から見るとそんな「差」をつけられるような要素あるか?って感じの業態で、こんな「倍」みたいな差が出せるのは異次元に凄いことだと思います。
セブンイレブンはローソンやファミマに比べて一店舗あたり売上が圧倒的だ…っていう話は有名ですが、それでも1.5倍ぐらいですからね。
コンビニに比べて食品スーパーは「他と違うウリ」が作りづらい領域が多いだろうに、それで「倍」というのは尋常じゃないです。
クックマートの白井健太郎社長は最近本も出されていて、これも超良かったんで良かったらどうぞ。
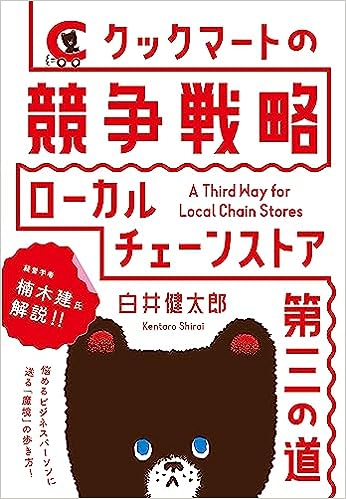
『クックマートの競争戦略 ローカルチェーンストア第三の道』
豊橋にある私のクライアント企業の経営者が、このクックマートの白井社長とお友達らしくて紹介されたんですが、時間が合わなくて白井氏御本人にお会いすることはできなかったものの、本を読んで店舗をいくつか見学しただけで「超すごい、やばい」感じが伝わってきました。
で、テスラの話と「あまりに違う」話題のように感じるかもしれませんが、
・”グローバルな共通性”を徹底的に押し込んで来るテスラ ・”ローカルの特殊性”を徹底的に育て上げるクックマート
…みたいな非常に対照的な話だよなあ…と思うわけです。
で、前編で書いたように、テスラっていうのは本当に「ごくごく一部の頭良い人が設計を徹底的に押し込む」ことで実現している会社という感じなんですよね。
で、テスラ車に限らずですが、「米国社会」というもの自体が、そういう「アホは黙って言う通りにしろ型運営」をやりまくることで、社会の末端レベルでの色々な「自己効力感」を奪いまくり、それが社会の不安定化を招いている側面は明らかにあるなと私は考えているわけです。
逆に日本では、クックマートのように物凄くうまく行っている会社以外でも、
「おベンキョーはまあそんなに得意じゃなかったけどね」
…というレベルの人の主体的な工夫を引き出して、市場的な「優秀性」につなげることで、単に他の社会にないクオリティを「金銭的に恵まれてない層」でも一応保持しているところがたくさんある。
それによって同時に、社会の末端で生きる人の「自己効力感」が米国型社会におけるように無茶苦茶になっておらず、それが社会の一応の安定に寄与しているところがある。










































