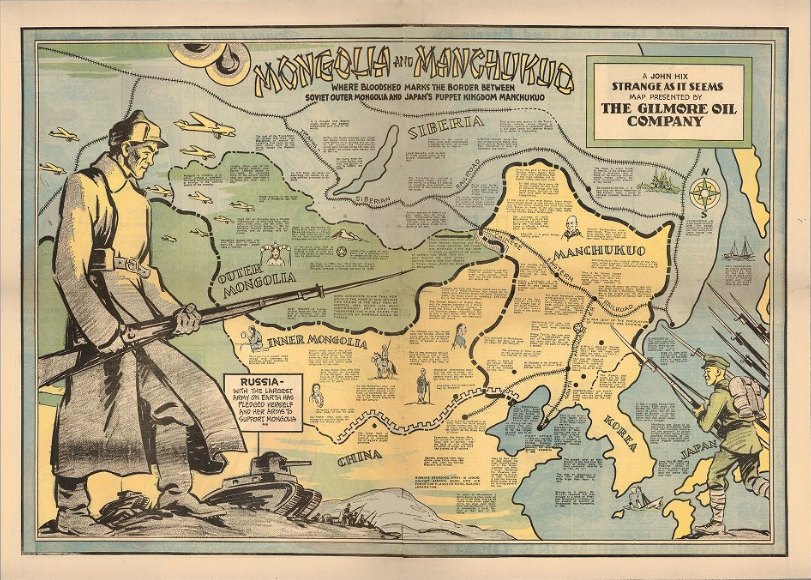
ソ連と日本の間の対立Wikipediaより
更に家永は、37年6月の乾岔子島事件は全面中国戦争突入(翌月の盧溝橋事件を指す)に先立ち、また38年7月の張鼓峰事件は漢口作戦に先立ち、それぞれソ連の動向を探るために日本軍が行った「威力偵察」だったとする「西村敏雄回想録」(関東軍参謀・最終階級少将)の記述を引き、「日本軍の側からソ連軍に仕掛けた局地戦であったことは、西村回想録が虚言でない限り、否定の余地がなかろう」と断じる。
(前回:日本が先に「日ソ中立条約」を破ったと主張する日本人学者(前編))
39年夏のノモンハン事件についても、家永は『朝鮮戦争』(洞富雄)の「各方面から推理してみた結果、ノモンハン事件は、関東軍司令部が、満・蒙間の歴史的境界線はどうであろうと構わず、満洲国の領土を強引にハルハ河の線まで押し広げようとして計画的に引き起こした軍事行動であったということを、ほぼ想定し得たと思う」との記述を根拠に、「関東軍の積極的攻撃意図が事件の発端となったことは、洞の推察の通りであったろうと思われる」と述べる。
そして日本は、ノモンハン直後の8月23日に独ソ不可侵条約が結ばれたことに呆然とし、41年4月に日ソ中立条約を締結したが、同年6月22日、ドイツが独ソ不可侵条約を破ると、支配層から「この機に乗じてドイツと呼応してシベリアを攻略すべきとの意見が強く主張され、南進を先とする主張と衝突して種々の経緯があったけれど」、7月2日の御前会議で「即時対ソ開戦論を抑えながら、解除条件付開戦意思が公式に決定された」と、関特演までの経緯を総括している。
「その後」についても家永は、「陸軍の期待に反してドイツ軍の対ソ作戦は進捗せず極東ソ連軍の大幅な西送は行われなかったし、日本も対米英開戦の方向へ傾斜していって到底ソ連領攻撃を実施する余裕を失ったため、「関特演」から実戦への意向は実現を見ないで終わった」が、それは「単に状況が有利とならず開戦の機会が到来しなかった結果に他ならない」と述べている。
家永への反証これら家永の主張に反証する資料には事欠かないが、ここでは、それまでの研究を覆した『ノモンハン事件の真相と戦果-ソ連軍撃破の記録-』(小田洋太郎・田端元:有朋書院02年刊)と防衛研究所主任研究官花田智之の報告書『ソ連の極東戦略と国際秩序』(20年)、講談社学術文庫の『パル判決書』(東京裁判研究会)と『私の見た東京裁判』(冨士信夫)及び『考証 日ソ中立条約公開された-ロシア外務省機密文書-』(岩波書店96年2月刊)を用いて、検討を加える。
東京裁判で46年10月8日から21日まで行われた、ソ連代表ゴルンスキー検事による日本の対ソ共同謀議の検察側立証は、04年の日露戦争での旅順における露国艦隊攻撃と真珠湾攻撃は「日本軍の一貫した観念」だとして始まり、18年のシベリア出兵に触れた後、22年の極東ソビエト共和国に対する日本の政策と31年の満洲国建国時の侵略的意図を同列視することを裁判官に要請した(パル判決書)。









































