「こちらの商品は『指定価格』対象となります」
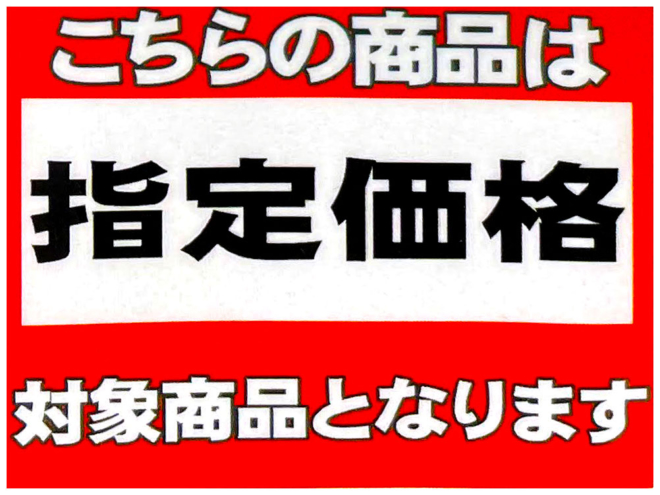
こんなPOPがついたパナソニック製品を、家電量販店で見かけるようになった。
指定価格とは、販売価格をパナソニック(パナソニック株式会社)が決めた価格に統一し、値下げを禁じる制度だ。製品が売れ残ったら、パナソニックが引き取る。滅失(めっしつ)・毀損(きそん)等の損害も負担する。瑕疵担保(かしたんぽ)責任も負う(※)。
パナソニックの目的は、値下げを防ぐとともに、製品ライフサイクルを長期化し、消費者ニーズに沿った製品開発を行うことだ。
家電は、販売開始から終了までの間に2割程度価格が下がる。メーカーは、下がった価格を引き上げるため、頻繁に新製品を開発・発売してきた。しかし、これが、製品ライフサイクルの短期化と、機能過剰な製品開発を招いていた。指定価格はこれを改めるためのものだ。
指定価格導入により、小売は在庫リスクから脱却できる。消費者はどこでも適正価格で購入できる。そして、メーカーは適正な利益確保ができる「三方良し」になる、とパナソニックはいう。
本当にそうだろうか? まず、パナソニックの利益状況からみてみよう。
メーカーの利益率は悪化傾向パナソニックが指定価格制度を導入してから3年。指定価格の対象製品の売上は、家電販売額の20%に達しており、「100億円規模の改善効果があった」という報道もある。
だが、日経の取材で「最近の成果」を問われたパナソニックの宮地晋治執行役員は、
回答を控える。
(パナソニック、家電2割で価格指定 取引見直し1年で倍増|日本経済新聞)
と、言葉を濁した。無理もない。数値上、目立った成果がないからだ。
制度導入以降のパナソニック家電(くらし事業セグメント)の営業利益率は、以下のように推移している。
2021年3月期:4.70% 2022年3月期:3.11% 2023年3月期:2.95%
少しずつだが、悪化しているのがわかる。今のところ「メーカー良し」とはなっていないようだ。今後、パナソニックは、指定価格対象製品の比率を、家電販売額の30%まで増やすとしている。

パナソニック プレスリリースより







































