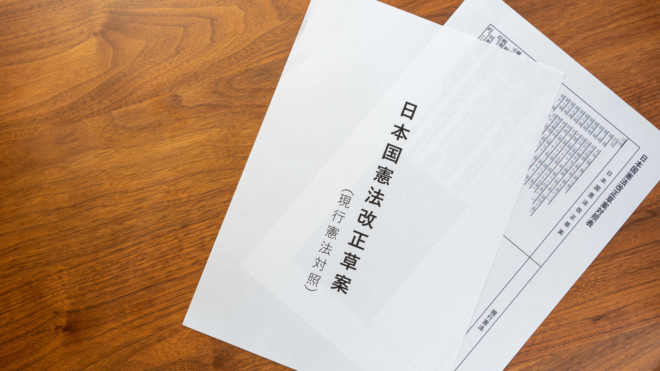
ururu/iStock
本日の憲法審査会では、緊急事態条項(議員任期の特例延長規定)に加えて、憲法9条について考えを述べました。
自民党の案や日本維新の会の案についても、一つの考え方ではありますが、折角、改正するのに、改正した後も「違憲論」が解消されない可能性があります。ここが最大の弱点です。
いわゆる「自衛隊明記論」は、自衛隊という「組織」についての違憲論が消えると思いますが、今の両党の案だと、自衛隊の「行為」、つまり行使する自衛権の範囲については、戦力不保持を定めた憲法9条2項を巡るこれまでの複雑な解釈を維持するとしており、結局のところ、改正後も、条文を読むだけでは自衛権の行使の範囲が不明のままなのです。例えて言うなら、お父さんが働く「職場」の違憲性は消えても、お父さんが「やっていること」の違憲性は消えないので、国防規定としても不十分だと考えます。
仮に、自衛権の範囲はこれまで同様、「解釈」に委ねることとし、「自衛隊の組織としての違憲性の否定」と「シビリンコントロールの明確化」のみを改憲の目的とするのであれば、むしろ、第5章「内閣」の章に、「必要な自衛の措置をとるための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」との規定を設けた方がいいのではないかと提案させてもらいました。
なお、9条を改正し、自衛権行使の本質を議論するのであれば、やはり、戦力不保持を定めた9条2項を残したままでいいのか、あるいは、自衛隊を「軍」して位置付けなくていいのか、自衛隊員は「軍人」ではないのか、国際法上の身分のあり方等も含めて、より本質的な議論を深めるべきだと考えます。
2020年12月にまとめた国民民主党の論点整理では、9条2項を存置する案と、存置しない案の2案の条文イメージ案を取りまとめて議論を継続しています。今後、憲法審査会でも、こうした自衛権を巡る本質的な議論を提起していきたいと思いますし、各党会派のご意見も伺いたいと思います。
本日の発言概要は以下のとおりです。










































