ここまで聞くとストイックすぎて自分には難しいと感じるかもしれないが、南雲氏は1日1食を勧めるものの、昼食を食べるなとまでは言っていない。
著書『「空腹」が人を健康にする(サンマーク出版 2012)』でも次のように書いている。

昼食を摂るとしたら、これもできるだけ少量にして、眠くなるほどは食べないこと。(中略)もし食べるなら、GI値が低いもので、血糖値が一気に上がらないようなものをおすすめします。
GI値とは食後の血糖値の上昇度を表す指数だ。実は昼食後眠くなる原因の一つは昼食後にGI値が急上昇するからだとされている。昼食後糖を摂りすぎると逆に、脳がエネルギー不足に陥ってしまうからだ。
糖を摂りすぎると脳がエネルギー不足に陥る理由脳科学者の西剛志氏の著書『脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる 低GI食 脳にいい最強の食事術(アスコム 2021)』によると、脳がエネルギーとして直接利用できるものは糖質(ブドウ糖)とされている。
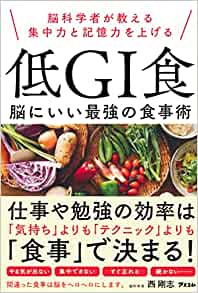
一方で糖質はたくさん摂りすぎると「血糖値スパイク」という現象が起き、脳のエネルギー不足を引き起こしてしまうという。
たとえば白米・パン・パスタなど糖質を含んだ食事をお腹いっぱい食べると血糖値が急上昇する。急激に上昇した血糖値を下げるために身体はインスリンを大量に放出する。その結果血糖値が急激に下がる。
そうすると、血液中の糖が不足し脳がエネルギー不足に陥る。脳のエネルギーが低下すると眠気や倦怠感が起きる。だから昼食で糖質を摂りすぎると一般的に眠くなるのだという。
こうした理由から著者の西氏は血糖値が急激に上がらない食事=低GI食を勧めている。西氏自身も午後に大切な作業や創造性の高い仕事をする時は昼食に糖質を大量にとらないように気をつけているという。
以上からも仕事のパフォーマンスを考えれば南雲氏も言ったように、昼食はできるだけ少量にして低GIのものを食べたほうがよいということになる。
一方で昼食をしっかりとらないとエネルギーが不足するのでは?と考える読者もいるかもしれない。
しかしたとえ昼食を全くとらなかったとしても、脳のエネルギー欠乏はありえない。そう指摘するのは遺伝学・栄養学博士の有馬佳代氏だ。










































