ロシアとウクライナの戦争は、さまざまな視点から論じられています。この戦争の原因について、リアリストの政治学者は、アメリカを中心とする西側がNATOを東方に拡大してウクライナを「事実上」のパートナー国にしようとしたことが、ロシアを存亡の危機に追いやったことを重視します。他方、中東欧を専門とする歴史学者は、ウクライナ属国化をもくろむプーチン大統領の現状打破的で収奪的な野心と攻撃性に注目します。
戦争の特徴についても意見が割れています。著名な政治学者や戦略研究者は、ロシアがウクライナに「予防戦争」を行ったと分析します。その一方で、歴史学者たちには、この戦争を「帝国主義的な植民地戦争」と位置づける傾向がみられます。
このようにロシアのウクライナ侵攻は同一の出来事であるにもかかわらず、論者によって説明の仕方が対称的になり、水と油のように混ざり合えません。では、何がこのような違いを生み出すのでしょうか。その答えは、国際関係研究における歴史学と政治学では、認識論と方法論が根本的に異なるからだということです。
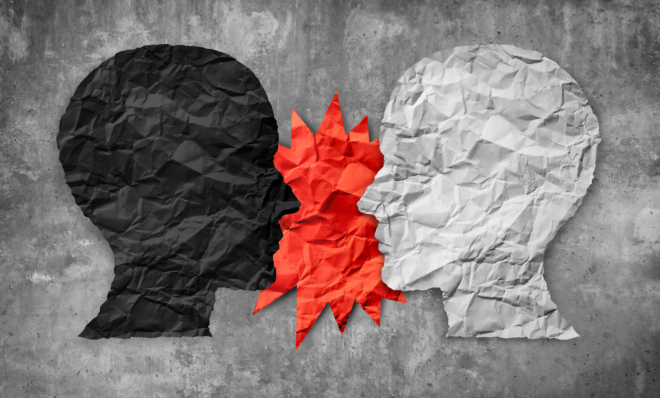
wildpixel/iStock
我が国の「国際政治学」では、政治学と歴史学が同じ学界で共存していますが、実は、両者は厳しい緊張関係にあります。政治学と歴史学は、戦争という同一のカテゴリーの事象を研究しますが、その分析や主張は、それぞれが依拠する方法が異なるので、必然的に対立するものになりがちなのです。とりわけ難しい問題は、戦争の責任追及や道徳的批判と原因の特定は、方法論上、それぞれ独立した作業になることが多く、必ずしも調和しないということです。

こうした両学問の特徴を明らかにして架橋することを試みたのが、今から20年以上前にまとめられた『国際関係研究へのアプローチ—歴史学と政治学の対話―』です。
本書では、北米の著名な歴史学者と政治学者が、それぞれの学問的作法を解説するとともに、第二次世界大戦といった本質的に重要な事例について、自分たちの認識論や方法論から分析して、歩み寄れるところと相反するところを明らかにするユニークな試みを行っています。
国際関係研究への政治学と歴史学のアプローチについて、代表的な学者の見解を整理して紹介します。①政治外交史研究者による歴史の道徳的判断の擁護論、②因果推論を重視する政治学者の価値中立的説明の擁護、③ナチス・ドイツの戦争に対する歴史学者と政治学者の異なる議論の順番です。











































