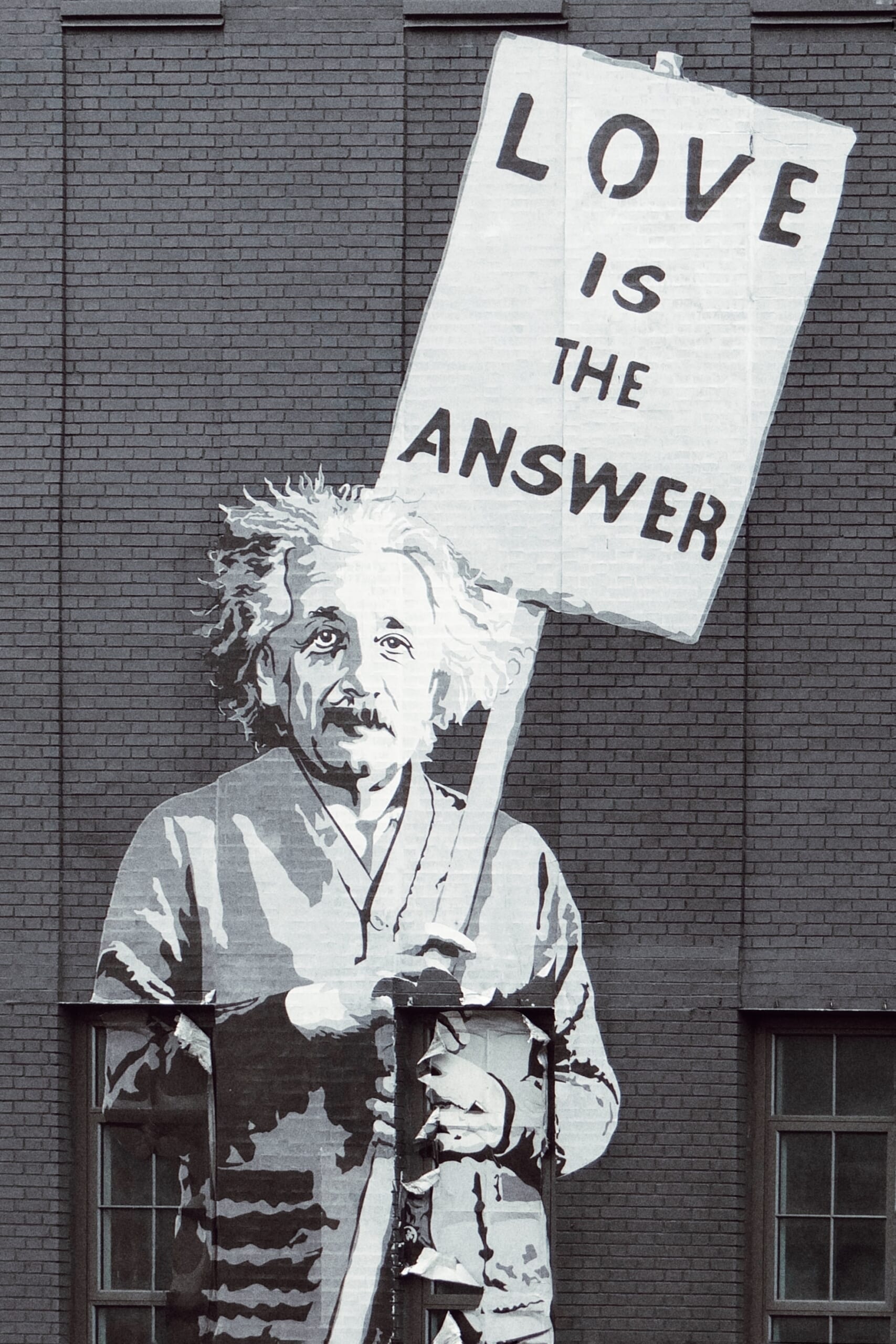
Ambiguous answer / Answering a question ambiguously
質問に対して曖昧に回答することで論点から逃げる
<説明>
「曖昧な回答」は、質疑応答において自分に不都合な質問から逃げるため、論点となる疑義に対して可否を十分に示すことなく曖昧に回答するものです。狡猾なマニピュレーターは、疑義と関連性をもつ言葉を散りばめることによって論点を【迂回 circumlocution】し、何とでも解釈できるような【曖昧 ambiguity】な回答を行うことで論点を無効化します。これは【論点曖昧】のテクニックを利用した【論点回避】と言えます。
論者Aが論者Bに質問QAをする。 論者Bが質問QAの疑義の可否を十分に示さずに回答する。 論者Bにとって都合が悪い質問QAの存在が忘れられる
<例>
<例1>
部品メーカー:我が社の部品をご利用いただけませんか。 機械メーカー:前向きに検討したいと思います。
「検討します」「検討したいと思います」「検討しています」「検討中です」は、しばしばビジネス上の方便として使われる曖昧な回答です。
<例2>
先生:机にマジックで落書きしたのは誰ですか? 生徒:誰かだと思います。
先生の質問の論点は、落書きした人物を特定することですが、不特定の人物を指す不定代名詞である「誰か」では人物を特定することはできません。
<例3>
警察官:あなたはスピード違反を犯しました。時速10kmオーバーです。 ドライバー:この道は深夜には誰も通行しません。事実誰も通行していません。時速10kmくらいオーバーしても誰にも迷惑はかかりません。 警察官:スピード違反は正しくない行為ですよ。そうでしょ? ドライバー:あなたは正しくないと思うかもしれないが、私は正しくなくないと思う。
「思う」という【認識 recognition】や「かもしれない」という【当て推量 guess】などの主観的なフレーズは曖昧な回答に多用されます。また、このドライバーは、個々の行為の効用を最大化することを善とする【行為功利主義 act-utilitarianism】の立場でスピード違反を正当化していますが、一般に法律は社会の効用を最大化する目的で立法機関が定めた規範に反する行為を悪として行政機関および司法機関が社会を運営する【規則功利主義 rule-utilitarianism】の立場に基づいています。
森羅万象が生じる現実世界の環境下において個々の行為の善悪の判定基準は自ずと曖昧になるため、規則功利主義に基づく法の遵守を義務として社会を運営することが、法治国家の現実的な手段と言えます。その意味で、このドライバーの主張は曖昧であり、妥当ではありません。










































