盆栽土の作り方は?

盆栽土の作り方は簡単です!
基本の盆栽土として、赤玉土の小玉を70%~80%、桐生砂または鹿沼土を20%~30%、腐葉土や堆肥を10%程度の割合で混合してみてください。そこから植物や環境にあわせてその植物が好む土に用土を数種類カスタムするのがいいでしょう。
ワンポイント
植え付けのとき、元肥や殺虫剤を一緒に混ぜ込みます。植物を植え付けた直後は鉢から水がしたたるまで、たくさん水やりをします。次回からは表面の土が乾いたら水やりをしましょう。盆栽土や気象条件により、水やりの頻度は変わります。
初心者には市販の盆栽土もよいですよ!
盆栽専用の土も販売されています。初心者の方やお忙しい方などは市販の盆栽用土がおすすめです。しかし、盆栽土の作り方としては混ぜ合わせるだけ。とても簡単に盆栽土を作れます。そのため、作り方を覚え、ご自身で植物にあわせてその植物の好む用土の配合が可能ですよ。
盆栽土の中身を解説!

市販の盆栽土の中身は赤玉土をベースに、桐生砂、腐葉土など数種類の用土が配合されています。野菜用の培養土や草花の培養土と比べ、排水性が良くなるように配合されています。
草花の培養土と違い、排水性を高めるために桐生砂や鹿沼土、ひゅうが土、川砂・山砂が入っています。保水性を高めるためには赤玉土や腐葉土が入っています。
草花用の培養土を持っている人は
もしお手持ちの草花用の培養土を使い、盆栽用土にしたいなら、排水性を高めるために、桐生砂や鹿沼土、ひゅうが土などをその植物の好む条件の土になるように混合してみてください。
次に土の種類別に役割を詳しく説明していきます。植える植物にあわせて、ご自身で独自に混合したり、市販の培養土に条件にあう用土を配合してみてください。
赤玉土
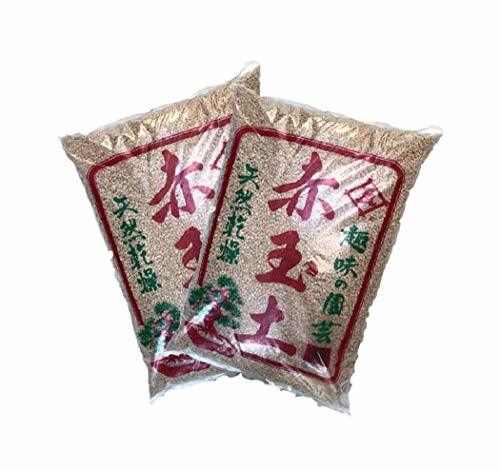
赤玉土は盆栽だけではなく園芸において広く使われています。粒の大きさで大玉、中玉、小玉、細粒にわけられ販売されています。販売されている園芸用土にはpHが表記されていて、赤玉土はpH6の弱酸性です。
赤玉土には保水性、排水性があります。やや粘土質のため、盆栽用土としては排水性を高めるために、桐生砂や鹿沼土と混合して使います。盆栽土として小玉~細粒をおすすめします。
桐生砂

桐生砂は通気性と排水性があり、通気性と排水性を高めたいときおすすめです。赤玉土やほかの用土と比べ、粒そのものが固く、通気性、排水性が失われにくいです。
桐生砂そのものに保水性もあります。盆栽土として赤玉土と混ぜて使われることが多い用土です。pH6程度の弱酸性で、多くの植物に対応しています。
鹿沼土

鹿沼土は多孔質(穴がたくさんあいている)で排水性と通気性があります。酸性の土なので、酸性を好む植物におすすめです。反対に、酸性を嫌う植物にはあまり向きません。
盆栽でもよくみられる、ツツジやサツキ、シャクナゲは酸性の土を好む植物です。鹿沼土を配合してあげることをおすすめします。
腐葉土

腐葉土は木の葉や木の幹を発酵させた堆肥です。腐葉土には2種類あり、腐葉土100%と表示されている商品は、木の葉のみを発酵させた比較的分解の早い堆肥です。通気性、保水性、排水性の3条件を向上させてくれます。また、堆肥中の微生物の働きにより、盆栽土に配合すると、ふかふかな土にしてくれます。
ひゅうが土
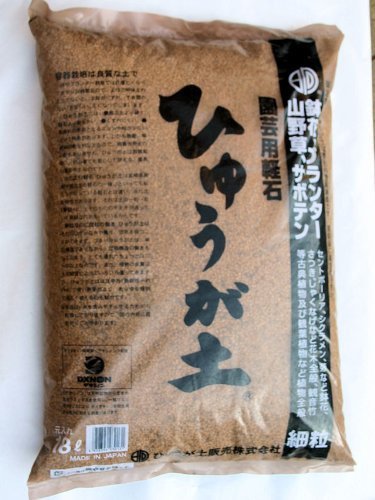
ひゅうが土は軽石の一種で、ボラ土とも呼ばれ、とても軽い土です。排水性を改善したい場合に配合します。鹿沼土のように多孔質ですが、ひゅうが土はpH値が6程度で、酸性を嫌う植物に配合されます。
川砂・山砂

川砂、山砂は排水性、通気性を向上させてくれます。保水性はないため、根腐れ防止に使用します。乾燥を好む植物に向いています。天然のものと違い、園芸用の川砂、山砂は加熱殺菌されているため、植物の根からの病気防止になります。
水苔

水苔は主に盆栽土の上にのせて使います。保水性、保温性があり、乾燥が苦手な植物や、冬場の凍結防止に使用されます。園芸用では乾燥させて販売されているため、水でやわらかくなるまで戻して使用します。
乾燥していない生きている種類の水苔も園芸店や通販で販売されています。生きている水苔は自分で増やし育てることもできます。
盆栽土の配合(ブレンド)方法は?

植物の好みに合わせて、赤玉土や桐生砂を大きな容器の中で、均一になるように混合してください。一般的に販売されている盆栽土は赤玉土を70%~80%、桐生砂や鹿沼土を20%~30%で混合されている場合が多いです。そのほかにもいくつかの種類の用土が混合されています。
季節や樹種、その植物の様子によって堆肥や肥料(元肥、追肥、お礼肥料など)、殺虫剤、活力剤を配合してください。
古い盆栽土は再利用できる?

使用した古い盆栽土は再利用できます。
使い終わった盆栽土をふるいにかけ、茎や根を取り除きます。次に、黒いビニール袋に土をいれ、湿る程度の水を入れ、袋を閉め、直射日光に1週間程度当てます。直射日光が害虫や病害菌を殺菌してくれます。殺菌後は堆肥や肥料を入れて再利用できます。
土のリサイクル材や土壌改良剤として、殺菌の工程を省いてくれる商品も販売されています。









































