天草からの入植者の痕跡
記録書のほかにも、郷土博物館の展示物の中には複数の天草ゆかりの品があります。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
この針箱は、天草から持ってこられたものと記録されています。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
使われていた農具にも地元とは異なる系統のものがあり、九州から持ち込まれたものと考えられているのだそう。
天草からやってきた人たちが、確かにこの土地で生活していたことが分かります。
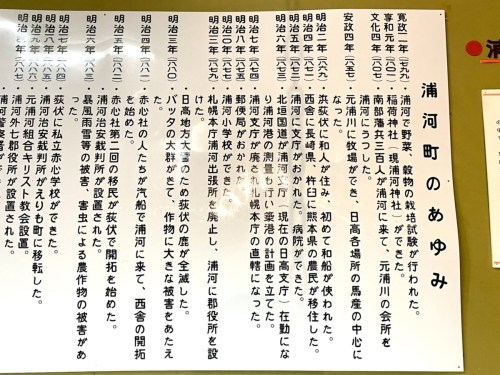
(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
伊藤さんのお話によれば、天草から移り住んだ90人余りの人たちの中で、つらくて逃げ出したりあきらめて天草へ帰ったりした人はいないとのこと。
寒さや雪、ヒグマなど九州とは違う苦労もある中で開拓者として精進され、しっかりとここで生活されたようです。
静寂の杵臼神社へ

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
天草から移り住んだ人たちが暮らしていた杵臼(きねうす)地区。集落の人たちの手でまつられた神社があると聞き、やってきました。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
土地の名を冠した「杵臼神社」。きれいに整えられていました。
森を背にした神社は、雪の中で静寂に包まれています。聞こえるのは、雪を踏みしめる自分の足音だけ。はりつめたような空気感が心地よい場所です。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
キタキツネやエゾシカの足跡があちこちにあって(何なら人の足跡より多い説)、

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
境内を流れる小川は、真っ白に凍りついています。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
鳥居の外は、競走馬たちが駆け回る農場。明治時代初期には、周辺一帯が広大な原野だったのでしょうね。

(画像=『肥後ジャーナル』より引用)
何だか胸がつまるような、冷たくて美しい夕空でした。
天草の人たちは、ここでどんな暮らしだったのかな。
私は現代の熊本から札幌へ引っ越しただけでも、寒いとか雪だとかと大騒ぎしているのに、明治初期の開拓生活はどれだけ大変だっただろうと思います。









































