こんにちは。デザイナーのこげちゃ丸です。
あなたは、人前で話すのは得意ですか? ぼくは苦手です。小学校のとき、国語の授業で教科書を立って読むのも嫌いでしたし、学芸会では自らセリフのない「木の役」に手を挙げてました。
でも、仕事ではそうも言っていられません。人前で話さなくてはいけない場面は多いですよね。特にプレゼンは緊張しませんか? どんな職業にも通じることですが、プレゼンスキルは、デザイナーにとっても必要な能力のひとつです。では、話すのが苦手な人が上手なプレゼンをするためには、どうすればいいんでしょう。
さっそく答えを言うと、「資料の力」を借りればいいんです。見やすく分かりやすい資料は、聞き手だけでなくプレゼンターの助けにもなります。今回はプレゼンを一気に上達させる、とっておきのプレゼン資料の作り方についてお伝えます。
目次
プレゼン資料作成のコツ1. 導入は「問いと答え」の連打で聞き手をひきつけよう!
プレゼン資料作成のコツ2. スライドは「固定と変化」の対比で魅せよう!
プレゼン資料作成のコツ1. 導入は「問いと答え」の連打で聞き手をひきつけよう!
プレゼンで一番緊張するのはどんな場面でしょう。相手が偉い人のとき? それとも聞き手の人数が多いときでしょうか? ぼくが一番緊張するのは、聞き手が自分の話に興味がない素振りを見せたときです。
スクリーンを見ずに自分のノートPCを見ている人や、あくびをする人が視界に入ると、変な汗が出てきます。そうすると焦って早口になったり、注目を集めようとしてウケを狙ってはハズしたりと、悪循環になりがちです。
プレゼンは最初の2分で勝負が決まります。1分間ならどんな内容でも我慢してもらえますが、2分を過ぎても興味をかき立てられないプレゼンは最後まで聞いてもらえません。ぼくの経験則だと、3分は絶対待ってくれない。だから、最初の2分がとても大切なんです。
では、どうすれば聞き手に興味を持ってもらえるのでしょう。色々なアプローチがありますが、問いと答えの連打で聞き手の興味を引くのは、とても有効です。ここまでの内容をプレゼン資料風にまとめてみます。
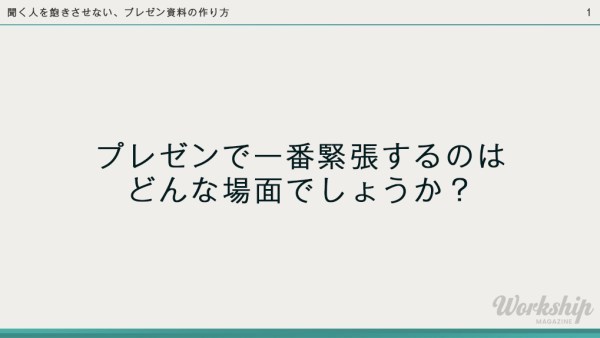
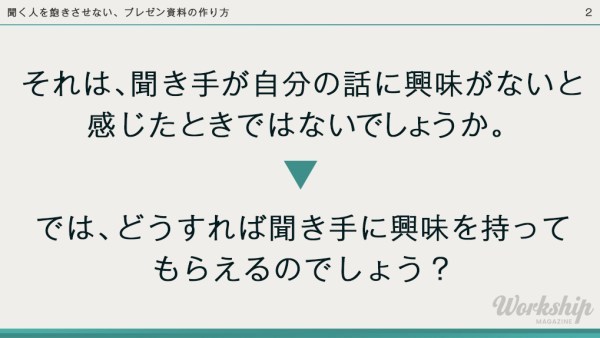
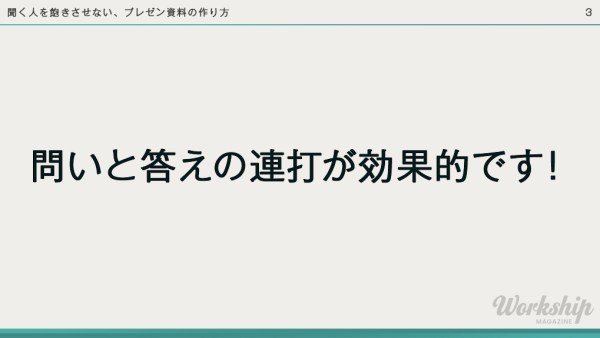
「この3枚のスライドは一枚にまとめられるのでは?」と思った方もいるかもしれません。でも、それはプレゼンの終盤、まとめページに適した見せ方です。
プレゼンの導入なら、テンポよく画面を切り替え、聞き手の注意を引き付ける方がいい。同じ画面で長々と話されると、それだけで聞き手の集中力が削がれてしまうからです。
質問形式にすると、聞き手が自分ごとに捉えてくれ、プレゼンに興味を持ってくれるメリットがあるんですよね。そして、問いの答えと次の問を併記することもポイントです。これによって、聞き手のモチベーションが持続してプレゼンを聞く気持ちになってくれるのです。
質問形式のメリットはもうひとつあります。プレゼンの導入は誰でも緊張するもの。頭が真っ白になって言葉が出てこない、ということもよくあります。だから、導入部分は話すこと全てをスライドに書いておけばいいんです。これなら、緊張してセリフを忘れても大丈夫。画面を見て、そのままを読めばいい。このように、聞き手に優しいスライドは、プレゼンターにとっても優しいのです。
プレゼン資料作成のコツ2. スライドは「固定と変化」の対比で魅せよう!
導入の次は、いよいよ本文です。聞く姿勢になってくれた参加者に思いの丈をを効果的に伝えたいですよね。プレゼンの内容はもちろん大事ですが、見せ方を変えるだけで印象がガラッと変わるんです。そのひとつが固定と変化で見せるやり方です。
このスライドをセオリー通りにつくるなら、スライドを2ページに分けて、それぞれの頁でパセリとトマトの写真をバーンと大きく使うべきです。
1ページにつき画像は1枚まで、メッセージラインと一緒に入れる……なんてセオリーもよく聞きます。でも、セオリー通りのプレゼン資料は単調になりがちです。コース料理の途中にお口直しのシャーベットが出てくるのも、料理のリズムを変えてメインディッシュをより美味しく食べてもらう工夫ですよね。
毎ページ大写しの画像がドーンと出てくると、聞き手は見慣れてしまいます。だから、あえて緩急をつけるんです。スライドの一部だけが、じわぁっと変わるページがあると、「あれ? 見間違いかな?」とスライドに注目してくれます。アハ体験で脳が刺激される現象に似ていると思います。
導入は、テンポよくスライドを切り替えて、聞き手の集中力を上げていく。そして、プレゼンの山場である今日いちばん伝えたいことを言う前に、溜めをつくるんです。
事例に出したような、画面の一部が変わるスライドの他にも、余白を大きくとって中央に小さく文字を配置するなど、プレゼンの溜めをつくる方法はいくつかあります。そうすると、対比効果でプレゼンのメインメッセージが、より強く聞き手に届きますよ。









































