目次
+正月飾りとは?種類と飾る場所
+正月飾りを出す期間は?いつからいつまで飾るの?
+外した正月飾りを処分する方法
+正月飾りで新年を気持ち良く迎えよう
年末になると、新年に向けて正月飾りを飾る企業も多いでしょう。しかし、年に1回しかない行事であるため、正月飾りの正しい飾り方や、時期、処分する方法について悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、正月飾りの由来をふまえたうえで、正月飾りの飾り方から処分方法まで基礎知識を紹介します。
本記事の内容をざっくり説明
- 正月飾りとは?種類と飾る場所を紹介
- 正月飾りを出す期間
- 外した正月飾りを処分する方法
正月飾りとは?種類と飾る場所
「正月飾り」と一口に言っても、さまざまな種類があります。
まずは正月飾りの種類と、飾る場所をご紹介します。種類によって飾る場所が決まっているものもあるので、間違った場所に飾らないように注意しましょう。
正月飾り1:門松

定番の正月飾りである「門松」。一般的には、2つで1対として「門」の位置に飾ります。
門松は、神様が空から降りてくるのに目印となるものといった意味があり、年神様を会社に迎え入れるために設置します。
竹の切り口が斜めの門松は「そぎ」、切り口が地面と平行のものは「寸胴」と呼ばれています。切り口を斜めにすることで節が切られてしまうため、「お金などをしっかり貯める」という意味で節を切らない「寸胴」のものをよいとしている地域や企業もあります。
門松を新しく準備するときには、どちらのデザインのものにするのか確認しておくといいでしょう。
正月飾り2:しめ飾り

「しめ飾り」は、飾っている場所が神様を迎え入れるのに清浄な場所であることを示すものです。
そのため、正月飾りの「しめ飾り」は、玄関やオフィスのドアの正面、裏口などに飾ります。ひとつだけではなく、複数飾ることもあるため、まずはしめ飾りを設置したい場所を決めておきましょう。
しめ飾りは、大きさによって呼び方が変わります。設置する場所によってサイズを決めて選ぶようにするとよいでしょう。
しめ飾りの大きさ別の呼び方
- 大根しめ:60m~180mなどの大きなしめ飾り
- ごぼうしめ:大根しめよりも小さな縄で作られたしめ飾り
- 輪飾り:最も小さく、簡易的なしめ飾り
正月飾り3:破魔矢

「破魔矢」は、神様を敬う気持ちを表すための正月飾りです。
破魔矢を飾るときは、敬う気持ちを示すためにも、目線よりも高い位置にある神棚や梁に設置することを忘れないようにしましょう。
正月飾り4:鏡餅

「鏡餅」は、神様への最高のお供え物とされている正月飾りです。
一般家庭でも定番の正月飾りである鏡餅は、みんなが集まる場所に飾られます。昔の日本では床の間に飾られていましたが、家の様式が異なる現在では大勢が集う場所に飾るのが一般的です。
鏡餅の飾り方は、三方と呼ばれる台の上に大き目の半紙を前方と両側にたらすようにして敷き、昆布・裏白・ゆずり葉などを乗せた上に餅を重ねておき、その上に橙(だいだい)を置くのが正式な方法です。
しかし現代では、このように格式張って飾ることは減ってきています。簡易的に半紙の上に餅を重ねるような飾り方でも十分でしょう。
また、橙(だいだい)はその呼び名から「代々栄える」という縁起があるものとされています。鏡餅の一番上に乗せるのは「みかん」というイメージがある人も多いでしょうが、最大限に縁起を担ぎたいのであれば橙を乗せるといいでしょう。
正月飾りを出す期間は?いつからいつまで飾るの?
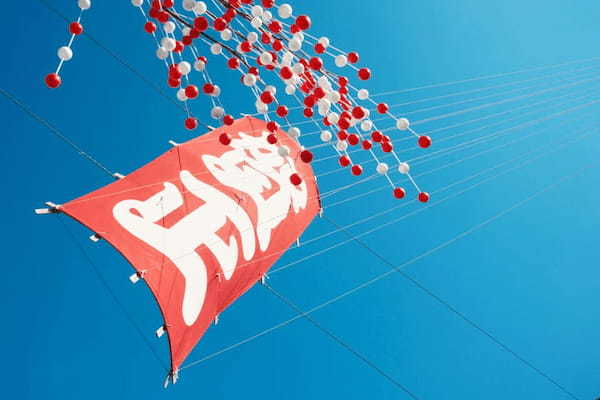
正月飾りは、年が明けた1月から飾り始めるものだと思っている人もいるのではないでしょうか。
実際は、1月からではなく12月の下旬には飾りつけをします。以下では、正月飾りを出すべき時期について詳しくご紹介します。
年神様を迎える準備は12月26日〜28日までに
正月飾りは、年神様(新しい年の神様)を迎えるための飾りつけです。
現在の日本では、クリスマスが終わった後の12月26日〜28日までに飾り付けるのが一般的です。ただし、クリスマスにこだわらなければ、正月事始めといわれる12月13日から飾り付けをしても問題がありません。
また、26日以降に正月飾りを飾るのは問題ありませんが、重要なのが「28日まで」に装飾を行うことに注意しましょう。
28日までに正月飾りを飾る理由は、29日は「二重苦」「苦に通じる」などの語呂合わせで縁起が悪いとされ、31日は「一夜飾り」で神様に対しての誠意が感じられないとされています。
どうしても28日までに飾り付けができなかった場合は、30日に正月飾りを飾りつけをするとよいでしょう。
松の内(1月7日まで)を過ぎたら正月飾りを外すのが一般的
正月飾りは、「松の内」と呼ばれる期間(元旦から7日まで)を過ぎたら神社に収めるのが一般的です。
しかし、地域によって小正月まで(15日まで)、二十日正月(20日まで)などばらつきがあるため、迷う場合は近所の人や職場の先輩に尋ねてみるのが無難です。
期間を過ぎても正月飾りを飾っているのは、「なんでまだ飾り付けをしているのだろう」と思われてしまうこともあります。正月飾りの意味を知らない企業のようにも見えてしまうため、飾る時期も大切ですが、正月飾りを外す時期についてもきちんと覚えておきましょう。









































