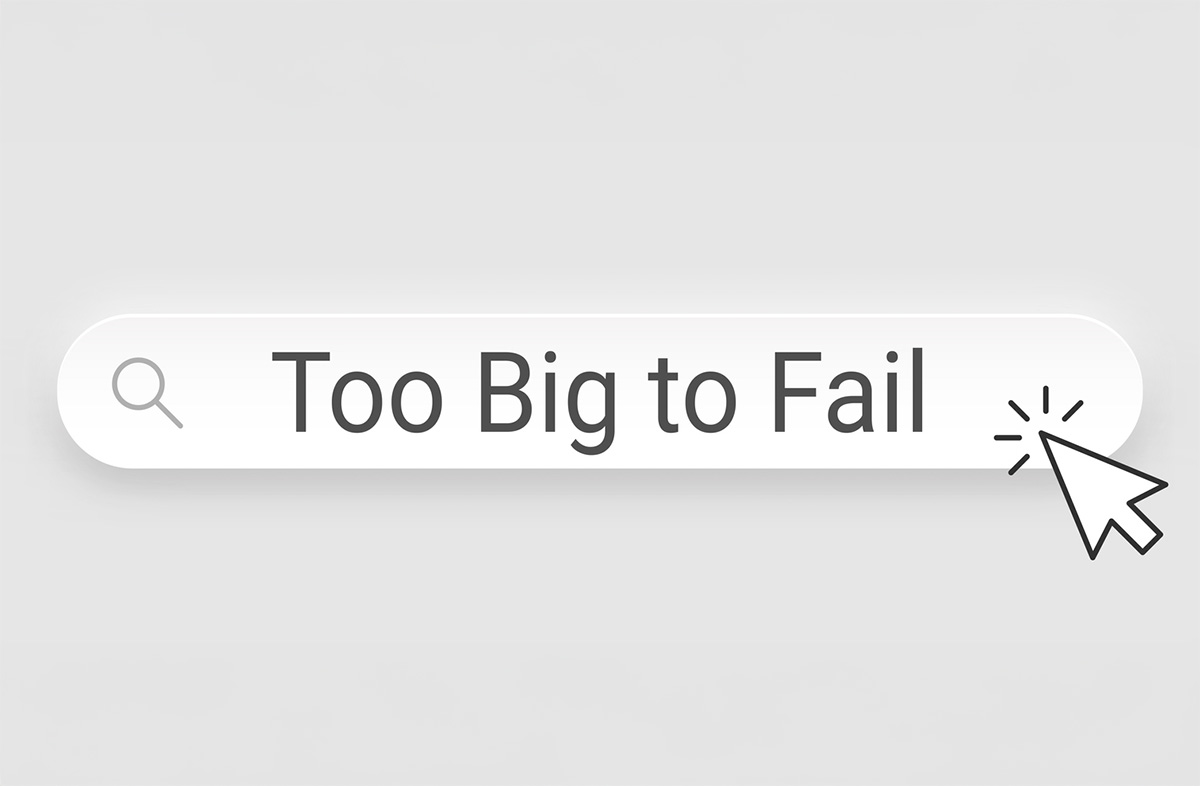
bgblue/iStock
経済危機になると、巨大企業は「大きすぎて潰せない」とされて、政府による救済の対象になるのはよくある話だ。
だが、科学の世界では話は別かと思いきや、似非気候科学に金が絡むと、明白に誤った論文ですら撤回されない、すなわち「大きすぎて潰せない」という事態がおきている。
しかも犯人は、最も権威ある学術雑誌であるネイチャーと、世界の金融機関が利用している「金融システムグリーン化ネットワーク(NGFS)」だ。
このNGFSに従ったCO2の削減計画に携わっている企業担当者の方も読者の中におられるだろう。それが、実はとんでもない似非科学に基づいているというのだ。
問題点指摘したのは、米コロラド大学のロジャー・ピールキ-Jr.教授だ。自身のSubstack「The Honest Broker」において「Too Big to Fail-A Major New Scnadal in Climate Science(大きすぎて潰せない──気候科学における新しい大スキャンダル)」と言う記事を2025年8月15日に発表した。
内容は、これまた気候科学では最も有名な機関の一つであるポツダム気候影響研究所(PIK)が主導したネイチャー誌の掲載論文(Kotz, Levermann & Wenz 2024)と、それを基にして金融当局が利用している「NGFSダメージ関数」の問題である。なお、ダメージ関数とは、地球温暖化による経済損失を、気温上昇の関数としてあらわしたものだ。
この論文は「地球温暖化が経済に及ぼす損害は従来想定より遥かに大きい」との結論で、はばひろくメディアで取り上げられた。
だがこの研究は、そもそも気温上昇だけで各国の経済成長率を説明しようとする強引かつ未検証な手法を採用していた。経済成長とは、技術革新、人口動態、政策・制度など多様な要因で左右されるにもかかわらず、それらを無視して、気温との単純な相関を計算し、それを因果関係とみなしたのである。統計的にもきわめて不安定なモデルであり、偶然のノイズや外れ値を「気候の影響」と誤解する危険を孕んでいた。










































