呼吸が心と脳をつなぐ仕組み
研究では、42人の参加者が20〜30分間のHVBセッションを体験。その結果、心拍数の上昇以外に副作用はなく、参加者は恐怖心やネガティブな感情が減少したと報告した。
MRIスキャンで脳内を詳しく見ると、興味深い変化が起きていた。HVBは脳全体の血流を減少させる一方で、感情や記憶を司る「右扁桃体」や「前部海馬」といった領域の活動を活発化させたのだ。研究者は、これにより感情的な記憶の処理が促進される可能性があると考えている。
一方で、身体感覚の認識に関わる「左頭頂弁蓋部」や「後部島皮質」の血流は減少し、この活動低下が強い変性意識状態、つまり「自己と世界の境界が曖昧になる」ような感覚と関連していた。カーター氏は、「これらの領域の血流が減少することで、自己の身体が自分のものであるという感覚が揺らぎ、参加者が報告したような特殊な精神状態の一因となっているのかもしれません」と説明する。
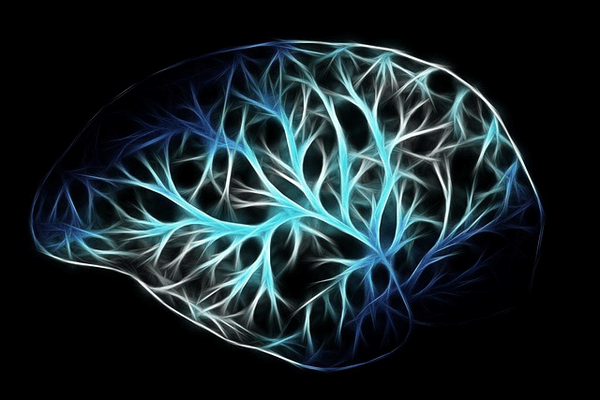
東洋の伝統から現代のセラピーへ
音楽と呼吸法を組み合わせる実践は、決して新しいものではない。そのルーツは、特に東洋の精神的・治癒的な伝統に深く根ざしている。中国の道教における気功や導引、チベット仏教の僧侶たちが行う詠唱と呼吸を合わせた瞑想、さらには中央アジアやシベリアのシャーマニズムに至るまで、人類は古くから呼吸をコントロールすることで意識の状態を変化させてきた。
意識探求で知られるモンロー研究所の専門家、ルイージ・シャンバレラ氏は、「呼吸は、心と体の交差点に位置しています。そして、普段は無意識に行われている体の働きの中で、唯一、意識的にコントロールできるものなのです」と語る。特に、息を吸う時間よりも吐く時間を長くすることで、体をリラックスさせる副交感神経の働きが活発になり、穏やかで広がりのある精神状態に入りやすくなるという。










































