それが、日本の言論空間における暗黙の常識なのである。そんなことは、他の宗教でも政党でもありえない、不思議なことである。
単行本も、一般向けの創価学会や公明党に関するものは、ほとんどがアンチ感情を満足させるように書かれたものである。一方、創価学会や公明党では、このところ少し前向きの変化が見られるが、内部への説明はものすごく丁寧であるのに対し、外部へ声高に主張を展開することには同じだけのエネルギーを使ってこなかったように見える。
そこで、小学館新書から一昨年刊行した『日本の政治「解体新書」──世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』で、「創価学会、公明党だけがなぜ成功したのか」というテーマの一章を書いたところ、創価学会の方からもアンチの立場の人からも、客観的で公正だ、長年の疑問がいろいろ解けたと評価をいただいた。
そこで、おおまじめに、創価学会とはなにか、公明党との関係はどうなっているかについて、長年研究してきた成果を一冊の本にまとめてみた。
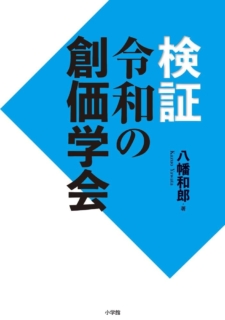
創価学会についての本といえば、佐藤優さんのように称賛するポジションが明確なもの、田原総一朗さんのように弁護するというような色彩が強いものもあるし、島田裕巳さんや小川寛大さんのように批判色がやや勝ったものもあるが、私のものは、歴史や世界の宗教のなかでの特色などを踏まえて、骨太に客観的な姿を描いていこうというものである。
基本的には好意的であるが、その理由について、創価学会や公明党はトヨタやパナソニックに似ているという指摘をし、長期にわたって成功し続けている組織は、基本的にそれが優れた組織であるがゆえだというポジションである。それを私は、「顧客満足度の高い組織である」と称している。
この本は、基本的には一般の人たちを読者として想定したものである。この日本最大の宗教と、連立与党の一角を占める巨大組織をもっと一般の人に知ってほしいと思っている。一方、創価学会や公明党の人たちに対しては、一般の人たちに対してはこういうふうに説明したらどうかという提案である。また、海外への広宣流布(布教)へ進むにあたって考えるべきことは何かも詳しく論じている。









































