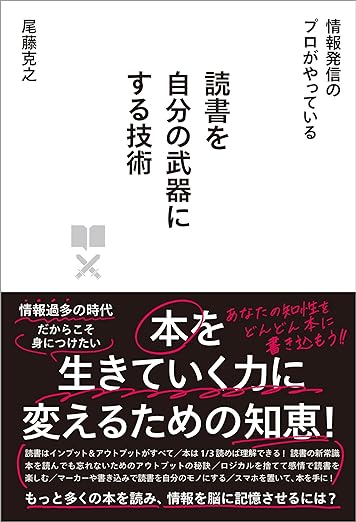では、どのようにして個々の患者に最適な治療を見つけることができるでしょうか。まず重要なのは、「スタート・ロー、ゴー・スロー」の原則です。つまり、低用量から開始し、ゆっくりと増量していくことです。これにより、副作用を最小限に抑えながら、その患者にとっての最適用量を見つけることができます。
次に、定期的なモニタリングが欠かせません。認知機能検査だけでなく、日常生活での変化を家族が詳細に記録することが重要です。「以前より穏やかになった」「夜間の睡眠が改善した」といった小さな変化も、治療効果を評価する重要な指標となります。
また、薬物療法と非薬物療法の組み合わせも個別化の重要な要素です。音楽が好きな患者には音楽療法を、社交的な患者にはグループ活動を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。
家族ができること
家族は、患者の最も身近な観察者として重要な役割を担います。服薬前後の変化を具体的に記録し、医師に伝えることが大切です。「薬を飲み始めてから表情が明るくなった」「午後になると落ち着きがなくなる」など、時間帯による変化も含めて観察することで、より適切な治療調整が可能になります。
認知症治療に「万能薬」は存在しません。しかし、患者一人ひとりの特性を理解し、きめ細やかな調整を行うことで、その人らしい生活を支える治療は可能です。個別化医療の実現には、医療者と家族の密接な連携が不可欠なのです。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)