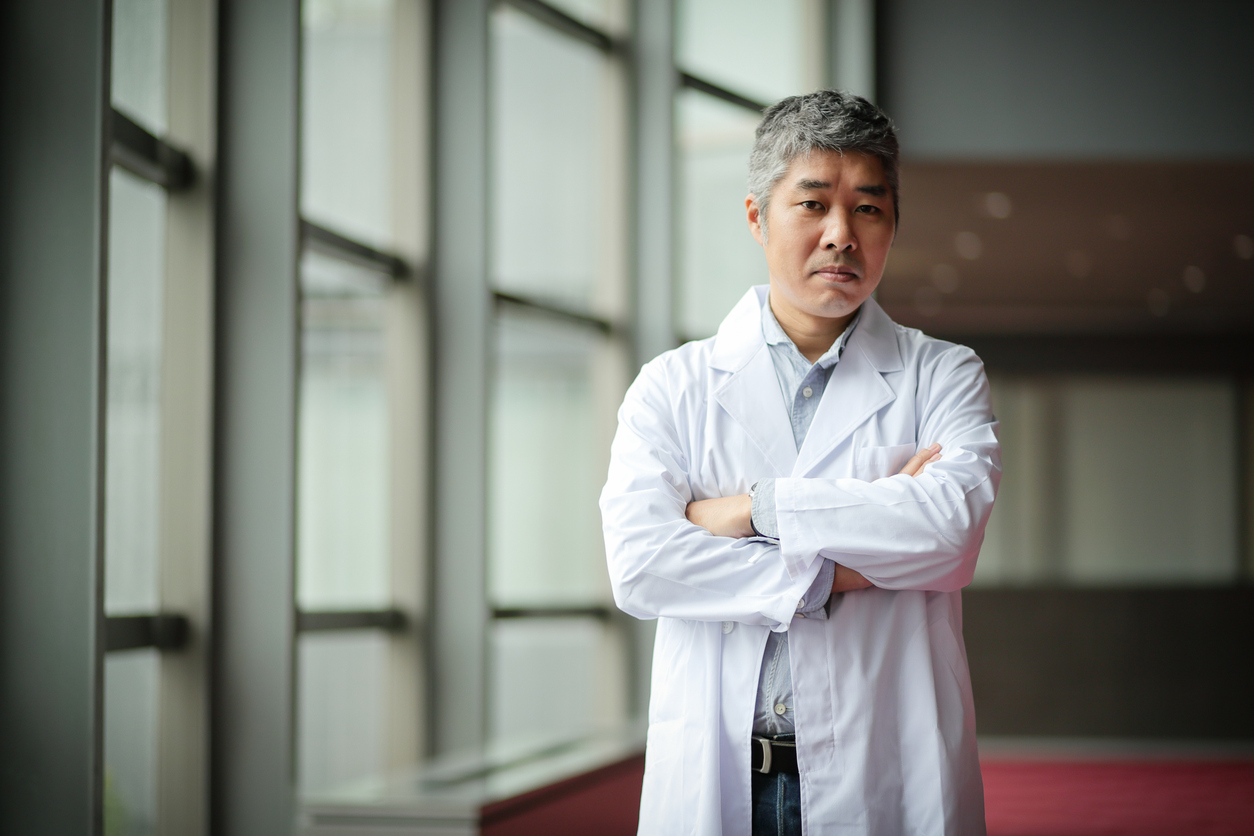
mokuden-photos/iStock
「○○会社の社長さんですか」。診察室でこんな会話が交わされた瞬間、医師の態度が急変する。これは決して珍しい光景ではない。医療現場における「VIP待遇」は、表向きは否定されながらも、実際には根強く存在している。

「知ってはいけない医者の正体」(平松類 著)SB新書
■
テレビドラマなどで、政治家や大企業の役員が来院すると、院長自ら挨拶に来ることがある。通常は研修医が担当するような初診でも、部長クラスの医師が直接診察することがある。待ち時間もほとんどなく、個室の待合室に案内される。
一般患者が2時間待ちの中、わずか10分で診察室に入れるVIP患者。この差は何を意味するのか。
医師側の本音も複雑だ。社会的地位の高い患者には慎重にならざるを得ない。弁護士や医療関係者が患者の場合、説明不足や医療ミスを指摘される可能性が高いため、通常より丁寧な対応を心がける人も多い。逆に言えば、一般の患者に対しては「このくらいの説明で十分だろう」という手抜きが生じている可能性がある。
経済格差も診療に影を落とす。自由診療を選択できる富裕層と、保険診療に頼らざるを得ない一般層では、受けられる医療サービスに明確な差が生まれている。
がん治療においても、高額な自由診療の免疫療法を受けられる患者と、標準治療しか選択肢がない患者では、医師の関わり方も変わってくる。「お金を払ってくれる患者には時間をかける」という経済原理が、医療現場にも浸透しているのだろう。
このような格差は、患者の健康格差をさらに拡大させる。適切な治療を受けられなかった患者は、症状が悪化してから再受診することになり、結果的により高額な医療費がかかることになる。また、医療不信から病院を避けるようになり、予防可能な疾患で命を落とすケースも少なくない。
医学教育の現場でも、この問題への取り組みが始まっている。「医療倫理」の授業で、無意識のバイアスについて学ぶカリキュラムが導入されている医学部も増えてきた。しかし、長年の慣習を変えることは容易ではない。










































