
takasuu/iStock
「パパ、なんでツーブロックは禁止なの?」――教育実習中の娘からの率直な疑問は、長年生徒指導を担当してきた著者にとって、まさに盲点を突かれた瞬間でした。学校では「厳しい先生」として通っていた著者が、家庭では娘の容赦ない質問に答えられずにいたのです。
この体験は、校則を巡る現代の深刻な問題を浮き彫りにします。教員も保護者も「子どものために」という同じ思いを抱いているはずなのに、なぜ校則については理解し合えないのでしょうか。
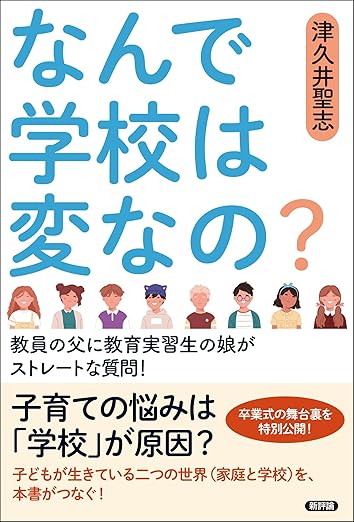
「なんで学校は変なの? 教員の父に教育実習生の娘がストレートな質問!」(津久井聖志 著)新評論
教室と家庭での温度差
学校現場にいる教員にとって、校則は「集団をまとめるための必要なツール」という側面があります。40人近い生徒を相手に授業を行い、学校行事を運営し、進路指導を行う中で、一定の秩序とルールは不可欠です。髪型や服装についても「きちんとした身だしなみが学習への取り組み姿勢につながる」という信念を持つ教員は少なくありません。
一方、家庭にいる保護者にとって、子どもは唯一無二の存在です。その子らしさや個性を大切にしたいと思うのは自然な感情です。学校で画一的な規則に縛られる我が子を見ていると、「なぜそこまで細かく規制する必要があるのか」という疑問が湧くのも当然でしょう。
特に現代の保護者は、自分たちが学生だった頃よりも個人の権利や多様性について敏感です。SNSなどを通じて他校の校則と比較する機会も多く、「うちの学校だけ特別厳しいのでは」という不満を抱きやすい環境にあります。
この溝を深めているのは、決定的なコミュニケーション不足です。多くの学校では、校則について保護者に詳しく説明する機会を設けていません。入学説明会で校則集を配布し、「学校のルールですので守ってください」と伝えるだけで終わってしまうケースがほとんどです。
教員側も、なぜその校則が必要なのかを論理的に説明する準備ができていないことが多いのです。「校則だから」「昔からそう決まっている」「他の学校でもそうしている」といった説明では、疑問を持つ保護者を納得させることはできません。










































