SFが現実になり、人類初の光駆動浮揚システムが開発されました。
2月12日に『Science Advances』に掲載された論文によれば、光を浮力に変換して重力圏内を飛行するディスクが開発されたとのこと。
信じがたい話ですが、論文が掲載された雑誌は権威のある『Science』系列であり、信ぴょう性は確かなようです。
しかし、いったいどんな仕組みで光を浮力に変えているのでしょうか?
目次
- 光をあてると浮遊する不思議ディスク
- カーボンナノチューブは空気分子を加速して放出する
- 移動方向の制御も可能
光をあてると浮遊する不思議ディスク
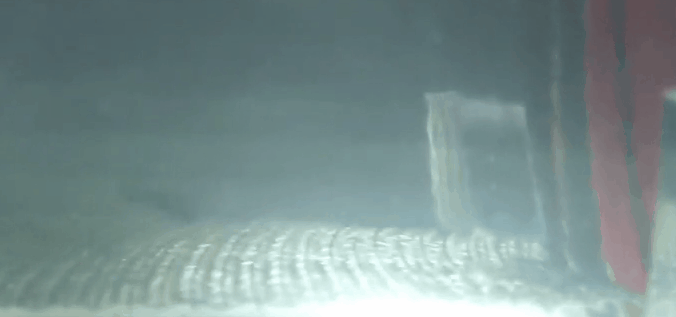
現在、大気圏内で空を飛ぶために使われている仕組みは、飛行機のように動力を使うか、気球のように空気の比重を利用する方法がメインになっています。
しかし飛行機や気球の飛び方が上手くいくのは、空気の密度が比較的濃い成層圏(11km~50km)までであり、より高い位置にある中間圏(50km~80km)では通用しません。
中間圏の空気密度は、エンジンで空気を押し出す必要がある飛行機や、比重の差によって飛ぶ気球にとっては薄すぎます。
また、さらに上空を飛行する人工衛星にとっても、中間圏は飛行できない領域です。
遠心力で飛行する人工衛星にとって、中間圏の空気密度は、飛行の邪魔になる空気抵抗を発生させるのに十分な濃さだったのです。
そのため、人類にとって、中間圏は通過するだけの場所と考えられてきました。
しかし今回、アメリカ、ペンシルベニア大学の研究者たちにより、中間圏でも飛翔可能な光駆動浮揚システムを備えたマイクロディスクが開発されました。
ディスクは薄い樹脂でできており、直径は6mm、厚さは800nm(0.0008mm)と非常に小型です。
もちろん、これだけでは光をあてても浮きません。











































