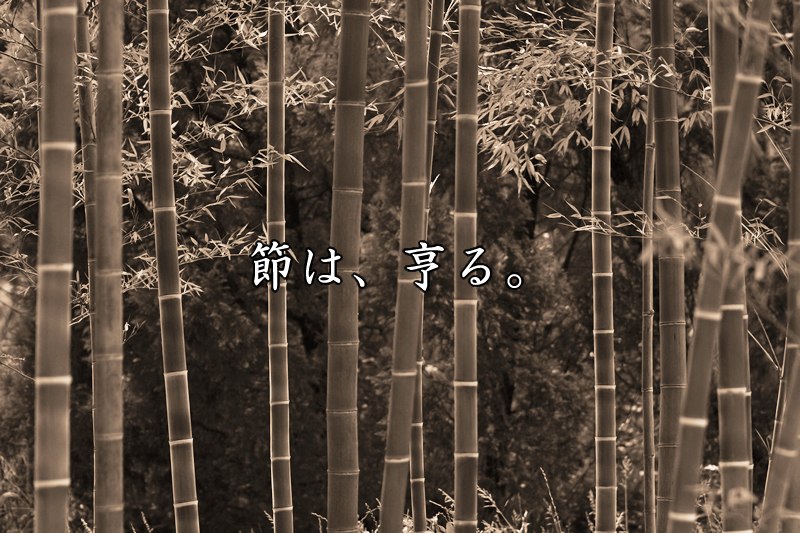
『孟子』の「離婁(りろう)章句下」に、「人(ひと)爲(な)さざる有るなり、而(しか)る後に以て爲す有るべし」とあります。中々味わい深い言葉だと思います。此の言につき、私が私淑する明治の知の巨人・安岡正篤先生は次のように述べておられます。
――世の中がどうなっておろうが自分はこういうことはしないんだというのが、「為さざるあるなり」である。これは理性と意思の力によって初めてできる。つまり、だらしのない人間の欲望や興味にまかせる生活に一つの締めくくりを与える、節をつけることである。それで初めて人間に「道」というものが立つ、これを義という。これを結んで「節義」と言います。
人間である以上、やるべき事・やってはいけない事が明確にあるということです。自分の「理性と意思の力によって」、やってはいけない事はやらず(節)、やるべき事はやらなければなりません(義)。
本田済著『易』で節の卦を見てみますと、「節(せつ)は、亨(とお)る。苦節貞(てい)にすべからず…節は竹のふしから、区切りがあって止まる意味になる。(中略)節ということは良いことなので、この卦に亨るの徳があるのは当然である。(中略)けれども節ということも度を過ぎれば本人を苦しめる。(中略)度外れた苦しい節というものは、これを常則として固執してはならない」と書かれています。
此の卦に関し安岡先生は「いろんな境遇、あるいは状況に応じて自由自在に応接、進歩していくためには、しっかりとした締めくくりがなければな」らず、「いわゆる節、節操というものが必要で」あり「それを説いたのが節の卦」だと言われています。易には、物事が行き過ぎぬよう節・節度といったものが必ずなければならない、とする考え方があります。私は、嘗て当ブログ「北尾吉孝日記」(15年8月25日)で次のように述べました。
――よく「節操がある」とか「節操がない」と言いますが、環境が変わると主義主張を簡単に変えて行く人が此の社会には沢山います。(中略)正しい選択をするために必要な三つの識(知識・見識・胆識)のうち、見識(…知識を踏まえ善悪の判断ができるようになった状態)を身に付けるには此の節操が必要なのです。(中略)節操のない人は、周囲の状況や意見に簡単に流されて、首尾一貫した態度が欠落して行きますから、何時まで経っても的確な判断はできませんし、周囲から信頼されることもありません。











































