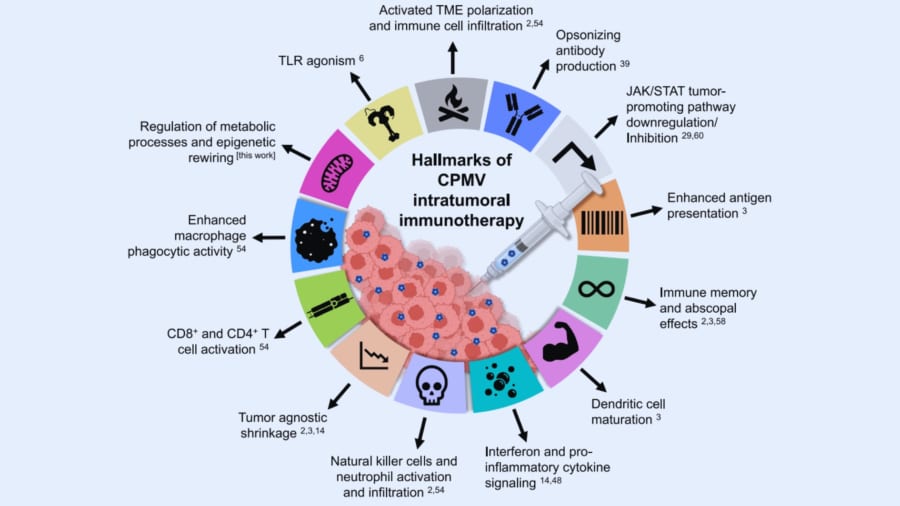この安定した長期的な刺激が、がん細胞への強い攻撃反応を引き起こす鍵だったのです。
一方、CCMVでは異なる状況が起こりました。
CCMVも同じように免疫細胞に取り込まれますが、そのRNAはエンドリソソームに届いても速やかに分解されてしまいました。
TLR7が刺激されることなく、免疫細胞は強い免疫シグナルを出すことができませんでした。
その結果、CCMVは免疫細胞に取り込まれても、がんに対する有効な免疫反応を引き起こすことはなかったのです。
まとめると、ササゲモザイクウイルスとCCMVの決定的な違いは、「RNAが細胞の中で安定して存在するか」と「免疫のセンサー(TLR7)をどれだけ強く持続的に刺激できるか」という点にありました。
ササゲモザイクウイルスはエンドリソソーム内でRNAが安定して存在することで、持続的にTLR7を刺激し、免疫細胞に強力なインターフェロンの産生を引き起こします。
これに対し、CCMVは同じ構造を持ちながらも、RNAが速やかに分解されてしまうため、強い免疫反応を起こすことができないのです。
また、研究チームはマウスのマクロファージ細胞を用いて両ウイルスの取り込みを詳しく調べました。
その結果、両ウイルスとも一般的な免疫細胞への取り込み効率に明確な差はありませんでした。
しかし、特定の受容体を介した取り込みの仕組みについては今回の研究では明らかにされていません。
別の研究では、ササゲモザイクウイルスが「スカベンジャー受容体A1(SR-A1)」という特定の受容体を介して取り込まれる可能性が示唆されていますが、本研究の範囲ではまだ確認されておらず、今後さらなる検証が必要です。
こうして、研究チームは、ササゲモザイクウイルスが他の植物ウイルスにはない独自の特徴を持っていることを実証し、その強力な抗腫瘍免疫反応の謎を解明しました。
この発見により、ササゲモザイクウイルスを利用したがん治療法をより効果的に設計するための重要な手がかりが得られたのです。
臨床応用目前?『畑生まれ』のがん治療薬の可能性