次の当たり前が、「生成AI」
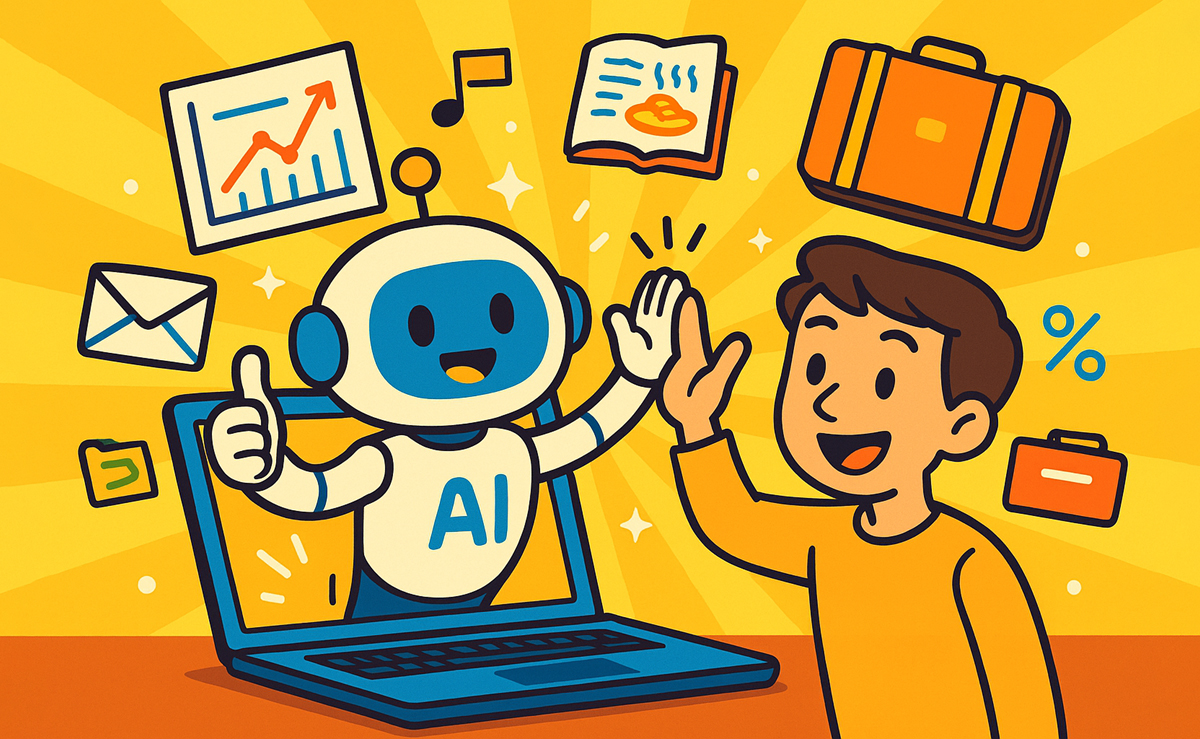
パソコンが職場に入ってきた90年代、「ワープロで十分っしょ」と言ってた人が今どうなったか。スマホが出てきた2007年、「ガラケーの方が電池長持ちだし」って言ってた人が今どこにいるか。…もうオチは見えてますよね?
2025年、同じことが生成AIで起きてます。「仕事も生活もぜ〜んぶAIに肩代わりさせたら、ムダ時間がごっそり消えたぞ?」という人と、「いや、なんか怖いし様子見…」で止まってる人。この差が、3年後とんでもなく開きます。中には「結果を勝手に拾ってくる」と検索エンジン程度と思ってる人がいて、どんなに裏で計算しているか、何十、何百ものニュースや論文を読み込んでいるかもしらん人が多すぎです。
今回の選挙なんてどの党に入れようかと思ったら、自分が大事に思うことは何かをまず前提としてAIに各政党の公約をすべて熟読させ、自分の理想とする世界に一番近くなる順に並べて貰えば良い。各党の公約とか全部読むのは大変だから本来、こういうのが向いているのです。
そこでAIを“パソコン&スマホ並みに”日常ツール化するコツを、仕事編/私生活編に分けてガッツリ紹介。さらに、
有料版vs無料版、どこが違う? AIを使わないと何がヤバい?シミュレーション 子どもに触らせるときのルール(宿題丸投げは絶対NG) 医者・エンジニアほか専門職のリアル活用術
まで詰め込みましたぜい
仕事編:AIを“同僚”にする7つのワザ
資料づくりは「AIひな形→人間ツッコミ」で時短
目的・ターゲット・ページ数をAIに投げる → 3秒で骨子が返ってくる。出てきた叩き台に「ここノリが暗い」「図を追加」など赤入れ。AIに再投げ。 結果:徹夜してた40枚の提案書が、早帰りデーに完成。プレストの前日には50本くらいアイデアのたたき台を出しておいてもらいます。
プロンプト例 「来週の役員会向けに、売上失速中の新規事業Aを立て直す5枚スライド作って。相手はDX弱者の60代役員。KPIは粗利率UP」で、前回の資料をpdfで読み込ませて書式と口調を合わせてもらう











































