群馬大学などで行われた研究により、糖尿病治療薬「イメグリミン」が膵臓でインスリンをつくる膵β細胞の数を増やし、細胞死を防ぐ仕組みが解明されました。
研究では膵β細胞の増殖と細胞死抑制には「アデニロコハク酸(S-AMP)」という代謝産物が存在することが重要であり、イメグリミンの投与により膵β細胞内でその量が約3倍に増加していることが示されています。
この発見は膵β細胞そのものを回復させる新しい糖尿病治療法につながる可能性があり、世界中で増え続ける糖尿病患者に大きな希望を与えるものです。
では、この小さな代謝産物はどのようにして膵β細胞を増やし、守るという働きを実現しているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月10日に『Diabetes』にて発表されました。
目次
- 糖尿病は膵β細胞の「過労死」――なぜ細胞を増やす治療が必要なのか
- 膵β細胞再生に重要な「S-AMP」を特定
- 「血糖値を下げる」から「細胞を増やす」へ――糖尿病治療を一変させるS-AMPの可能性
糖尿病は膵β細胞の「過労死」――なぜ細胞を増やす治療が必要なのか
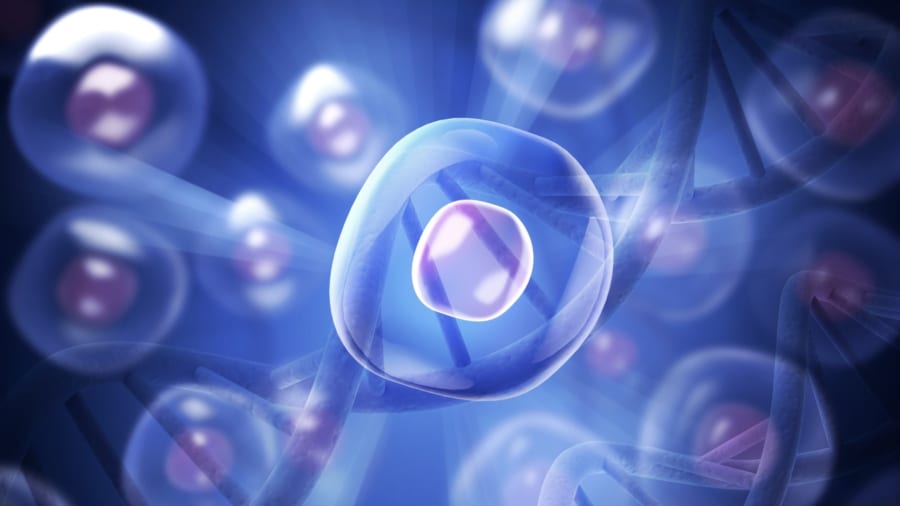
健康診断で血糖値が高いと指摘され、「このままだと糖尿病になりますよ」と言われた経験がある人もいるかもしれません。
実際、日本では成人の約4人に1人が糖尿病またはその予備群と言われており、もはや糖尿病は他人事ではありません。
糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気で、放置すると目や腎臓、神経に深刻な合併症を引き起こすこともあります。
だからこそ、血糖値を正常に保つインスリンというホルモンが非常に重要な役割を果たしているのです。
インスリンは膵臓にある膵β(ベータ)細胞から分泌され、血液中の糖を体の細胞に取り込ませて血糖値を下げる唯一のホルモンです。
ところが、肥満や運動不足、食生活の乱れといった生活習慣が続くと、このインスリンの効き目が徐々に悪くなってしまいます。











































