『世界のニュースを日本人は何も知らない BEST版』(ワニブックスPLUS新書) は、そのタイトルの扇情性に反して、実のところかなり正攻法な議論を展開している。むしろ、ここで描かれている「日本人の国際的無知」は、何度も繰り返されてきた指摘であり、本書が改めてそれを整理し、一般読者にも理解できるように噛み砕いている点に価値がある。
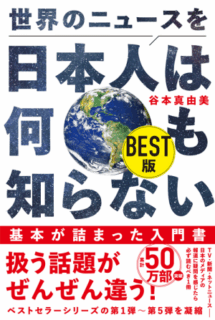
本書の出発点は、島国日本の特殊性だ。言語的にも文化的にも均質性が高く、外部との接触を最小限に抑えてきた歴史を持つ。これは、安定した社会形成にとっては有利に働いたが、同時に他者に対する関心の低さ、外部情報への鈍感さを育ててきた。この構造的な「情報的閉鎖性」が、現代日本の深刻な弱点になっている。

maruco/iStock
しかも現代は、通信インフラが整い、情報へのアクセスが過去に例を見ないほど自由になっている時代だ。物理的に海外に出る必要もなく、スマートフォンひとつで世界中の一次情報に触れられる。それにもかかわらず、海外ニュースに興味を持たず、自国中心の視野に閉じこもっている日本人の情報行動には、ある種の選択的無関心がある。
本書が批判するのは、単に個人の怠慢ではない。むしろ、情報の供給側、すなわち日本のマスメディアが構造的に「内向き」であることを問題にしている。テレビや新聞で報じられる国際ニュースは極端に少なく、あっても断片的で、日本人にとって心地よいように編集されている。よく言われる「外国人から見た日本は素晴らしい」といった類の番組が繰り返されるのは、その一例である。
このような情報環境の結果として、例えば難民危機の最中にギリシャへの新婚旅行を計画してしまう人が現れる。あるいは、治安の悪化したトルコを「異国情緒あふれる観光地」として能天気に紹介する雑誌が出る。これらの例は単なる笑い話ではない。情報の欠如は、生活や安全、そしてキャリアにすら直結する問題である。事実、欧米のインターンシップ制度の理解を欠いたまま、企業に履歴書を送り、「教えてください、給料もください」と訴える日本人学生のエピソードには、無知がどれほど国際社会で通用しないかが象徴的に表れている。










































