
京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 京都府教育委員会HPより
『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで –』(ワニブックス)の発刊を記念しての連続記事の8回目。テーマは旧制中学のカリキュラムである。
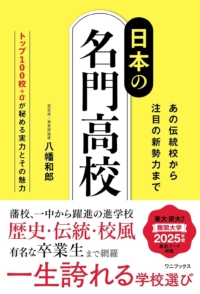
幕末になると、藩校でも洋学が教えられるようになった。幕府でも必要に迫られて蕃書取調所などが設けられたし、各藩でも研究や教育が開始されたものであり、明治になると競ってお雇い外人を招き、漢学を専門としていた教師たちは失業していくことになる。
たとえば、盛岡藩では、明治二年に南部利恭が転封されていた白石から復帰して盛岡藩を再建したので、戊辰戦争勃発から休校していた作人館を、あらたに洋学所を開設するなどして再開した。
明治3年になって財政難の盛岡藩は全国的な廃藩置県に先立って廃藩となり、盛岡県が置かれて、藩学作人館は県学校と改称された。そして、国学を中心として皇学、漢学、洋学、算学の四学科制が採用されたのである。
皇学科では、古事記、延喜式八之巻、日本書紀、古語拾遺が、漢学科では四書、春秋左氏伝、十八史略、元明清史略が、洋学科では英文典、地理書、理学訓導、算学科では和算、洋算(加法ヨリ開平立方ニ至ル)が教えられることとなった。
だが、明治4年には、「漢学休業候事」が県庁から出されて、洋学教育のみを行うこととなり、盛岡洋学校と改称した。そして、翌五年には、学制が発布され、従来の学校を一旦廃すことになり、作人館を継承してきた盛岡洋学校も廃校となったのである。
のちに京都一中(現在の洛北高校)となる京都府中学が開校したのは、明治3年であり、日本で最初の旧制中学校といってよいであろう。しかも、この中学は湯川秀樹、朝永振一郎という日本人ノーベル賞受賞者の第一号と第二号を輩出した。そして、戦後体制のなかで進学校としての栄光を失うに至った時代を経て、最近は中高一貫クラスの創設など名門復活へ向けての模索のなかにある。










































