武芸としては、高麗流馬術、日置流弓術、荻野流砲術、鏡知流槍術、柳生流と示現流剣術、狩野派絵画、和歌、点茶、囲碁、将棋、魚釣り、朝顔作りなどに励んだという。また、曾祖父重豪とともにシーボルトと会って見聞を広めたりした。
つまり、中国の古典を学ぶことにより、日常会話とはまったく違う漢文読み下し言葉を身につけ、あわせ倫理や処世術、それに歴史を学ぶことが「文」の主体であり、一方で武芸を一通り身につけたのである。
斉彬は頭脳明晰で優れた人物であったが、彼自身は特別に学問に傾斜したタイプではない。そういうことでは、むしろ、側室お由羅を母とし、鹿児島で育った弟・久光の方が、学者肌で勉強好きである。久光は昌平坂学問所で学んだ儒学者・上原尚賢を家庭教師に、漢学を学び、山崎闇斎の弟子である浅見絅斎が書いた中国の偉人たちの列伝『靖献遺言』を愛読し、「唐詩選」や「島津歴代歌」(島津歴代藩主の業績を詩に詠み込んだもの)や「いろは歌」(戦国時代の島津忠良が詠んだ家訓のようなもの)などを壁に貼って覚えたという。
江戸後期の殿様で出来がいい人たちはこんな形で育てられたのだが、上級武士の子弟は、これほど充実していなくても、よく似たタイプの教育を受けていたといえる。
だが、世の中にはそれほどたくさん優れた先生がいるわけでない。それに、一人で学ぶより切磋琢磨する方が能率も上がる。そこで、徐々に私塾のようなものが成立し、さらに、藩自身が経営する、藩校が生まれてきたのである。
それでは彼らほどできのよくないバカ殿たちはどうしたのかというと、ほとんど勉強しなかったのである。歴代の徳川将軍を見ても、国語・社会について大卒クラスの学力があったのは、5代将軍綱吉と15代将軍慶喜だけ、6代将軍家宣、10代将軍家治、11代将軍家斉、12代家慶、14大家茂がどうだったかというところだろう。

徳川綱吉 Wikipediaより
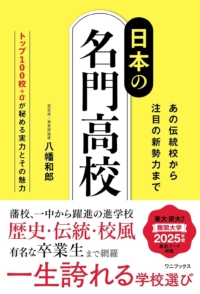
【目次】 はじめに 伝統の名門校から躍進する注目校まで 第1章 東京・神奈川の名門高校 第2章 関西の名門高校 第3章 中部の名門高校 第4章 東日本の名門高校 第5章 西日本の名門高校










































