『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで –』(ワニブックス)の発刊を記念しての連続記事の7回目。
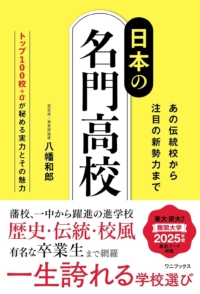
まず、本書の内容を動画にして三回に分けて公開している。ぜひ、ご覧いただきたい。
日本の名門高校トップ100!小中高は世界でもハイレベル!あの名門校から注目の新勢力まで、あなたの出身校は?
日本の名門高校トップ100!どんな基準で選んだか?〜地方の隠れた伝統校から躍進する首都圏進学校まで〜
日本の名門高校トップ100!医学部進学は人気ダウン傾向!中高一貫はどうなのか?
さて、今回から何度かに分けて、カリキュラムという視点から日本の中等教育の歩みを紹介したい。
江戸時代までは、ほとんどまともな学校が存在しなかった。平安時代には、大学寮などというものがあったことは、NHK大河ドラマ「光る君へ」でも紫式部の弟が学ぶ様子が描かれていた。
しかし、それすらなくなって、禅宗などの僧侶が大名や上級武士を家庭教師的に教育するだけになった。若いころに、寺に入って勉強していたという貴公子が多いのはそのせいだ。
江戸時代になっても同じようなものだった。幕末きっての名君といわれ、13代将軍家定の御台所となった篤姫の養父でもあった島津斉彬(文化6年、1809年生まれ)は、この時代の殿様として最高に恵まれた教育を受けた人物であった。

島津斉彬公像 鹿児島県観光サイトより
曾祖父である島津重豪、祖父の斉宣、父の斉興はいずれも好学で知られた大名だったし、それ以上に、母で鳥取池田家出身の弥姫(周子)は、嫁入り道具として漢籍を大量に持ち込んで薩摩藩士たちを驚かせたような女性だった。弥姫は息子である斉彬に対して教育ママぶりを発揮したし、斉彬もそれに良く応えた。
斉彬は5歳のころから読書・習字を開始し、11、2歳のころになると四書五経の素読を終えた。そして、17、8歳のころまでには二一史(史記から元史まで)という中国通史を習った。










































