Lenovo for start-upsとIVSの高い親和性
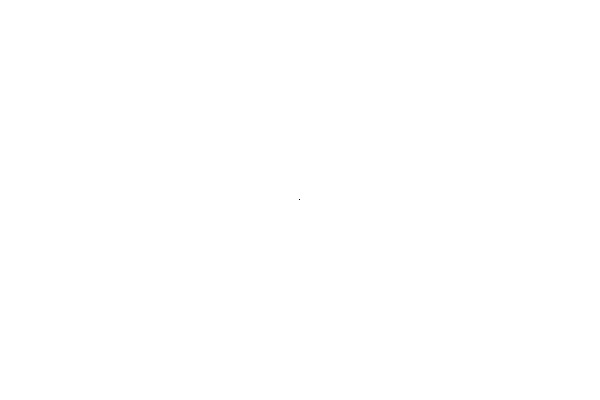
——Lenovoは昨年に引き続き、Lenovo for start-upsとしてIVS2025への出展を決めていますね。この出展を決めた理由を教えてください。
中田 :理由はおもに2つあります。 1つはLenovo for start-upsの周知、もう1つはスタートアップ起業の方々との関係づくりです。 根底には、Lenovo for start-upsを活用することで本業に投下するリソースを最大化し、成長するスタートアップ企業が増える、という流れをつくれればという思いがあります。
岡田 :実際、IVSに参加するスタートアップ企業の経営者のなかには、ハードウェアの調達やそれにともなうセキュリティ設定に課題を抱えている方も多くいます。とくに、1年間で100〜200名の採用を行うなど、急激な成長フェーズにある企業が多いですね。
中田 :セキュリティへの対策は、創業期だけでなく成長期にも課題になりがちです。取引が大きくなればなるほど、企業の情報管理体制を見られるようになりますし、セキュリティ周りの脆弱さはIPOの観点でも不利に働いてしまいます。
岡田 :対策が必要なことがわかっていても、どこにどうやってコストをかけたらよいのか、ハードウェアに対して適切な投資とはどのようなものか分からないことも多いです。 そういった方々に向けて、「こんなサービスがある」「サブスクリプションという選択肢がある」というところをアピールできるという点で、Lenovo for start-upsとIVSの親和性は非常に高いと考えています。
大局的に見た日本のスタートアップの課題とは
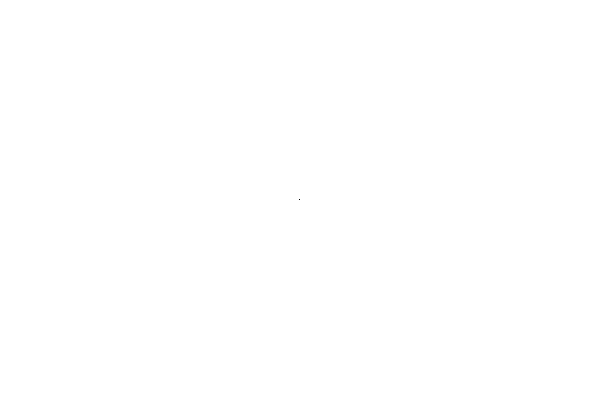
——LenovoとIVSは、ハードウェアとカンファレンスというそれぞれのアプローチでスタートアップを支援していますが、「日本のスタートアップ」という全体で捉えた場合、どのような課題があると感じていますか?
岡田 :日本はよくも悪くも、「国内で完結するマーケットがある」状況です。日本におけるスタートアップ企業数自体は増加しているものの、ユニコーン、デカコーンといわれるスタートアップ企業が登場しづらく、事業が大きくスケールアップしない要因になっていると感じます。
IVSを運営するHeadline Asiaは、東京のほか、台北にもヘッドオフィスを設けているのですが、現地の様子を見て事業拡大に対する文化の違いを感じます。 台湾などの場合、そもそも国外に出ていかないと企業規模の拡大が見込めません。国内だけでは“規模の天井”が見えてしまっているため、彼らは、最初から海外展開を見据えて事業を計画するのです。
中田 :日本は比較的、IPOへのハードルが低いことも、ユニコーン、デカコーン企業の登場が少ないことの要因になっているかもしれませんね。
岡田 :スタートアップエコシステム自体がまだ成熟しきっていないという部分も、原因の1つにあると思っています。とくに、成長段階のグロースステージにおける支援や投資が圧倒的に足りないと感じます。
中田 :あくまでアメリカとの比較になりますが、日本は、投資する主体となる企業が自社の新規事業へのシナジーを目的とする戦略投資が中心で、投資先の企業が大きく成長することによる金融的なリターンを目的としていない場合が多いため、ある程度のところで投資をしなくなるケースがあります。 これが、日本においてグロースステージに至ったスタートアップ企業への資金流入が、非常に少ないことの原因です。
メンターの性質の違いも影響しているかもしれません。 アメリカだと「アクセラレーター」と呼ばれる、スタートアップのプロフェッショナルが企業に常駐して、ITコーポレートをはじめ、スタートアップ企業の成長に必要な支援を次々と行っていきます。 一方、日本は大企業の上層部がメンターにつくケースが多いです。この場合、企業価値を何倍にするか? という観点ではなく、黒字化やIPOに照準を合わせた支援が中心になります。 これが日本の倒産率が低く、連続起業のテンポ感がよい理由でもあり、グローバル展開でのボトルネックにもなっている部分であると感じますね。






































