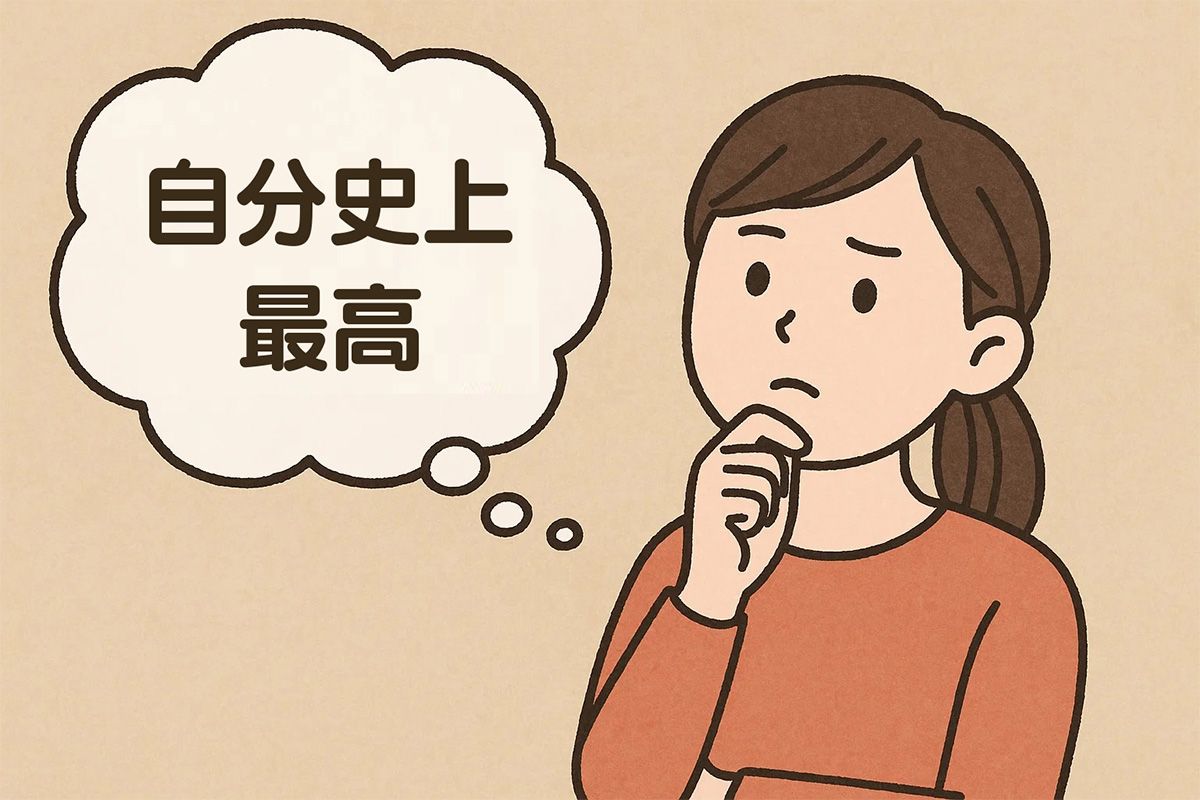
「今日の晩ご飯、自分史上最高においしい!」 「私史上最高の旅行だった」
SNSを開けば、こうした表現があふれています。かつて「史上最高」という言葉は偉大な歴史的出来事や記録に用いられてきましたが、いつからか「自分」や「私」という個人を示す言葉と組み合わせた用法が日常会話に浸透しています。
この言葉の変容は、私たちのコミュニケーションや世代間の認識の差にどのような影響を与えているのでしょうか。
言語学的に見ると、この表現は従来の「史上最高」から派生したものです。『広辞苑』によれば、「史上」とは「歴史上。また、記録に残っている限りにおいて」と定義されています。本来、人類の長い歴史や公的な記録を指す言葉が、個人の経験という私的な領域に限定される「自分史上」という造語的用法へと拡張されたのです。
この変化の背景には、SNSの普及による自己表現の多様化があります。国立国語研究所の調査「現代日本語における新語・流行語の定着過程」(2021年)によれば、「自分史上最高」という表現のSNS上での使用頻度は2015年から2020年の間に約8倍に増加しています。特に10代後半から20代の若年層での使用が顕著です。
先日、50代の上司に「これは部門史上最高の企画書です」と熱意を込めて説明した新入社員が、思わぬ反応に戸惑ったというエピソードを耳にしました。上司には大げさな表現に聞こえたようですが、本人は最大級の称賛のつもりだったそうです。こうした世代間のコミュニケーションギャップが生じる背景には何があるのでしょうか。
言語学者の井上史雄氏は著書『日本語ウォッチング』(2020年)で「新語や流行語に対して違和感を持つのは、言語変化の過渡期において自然な反応であり、特に40代以上の世代ではこの傾向が強い」と指摘しています。
「史上」という言葉が持つ荘厳さや重みと、個人的な体験を組み合わせることへの違和感も無視できません。「史上最高」は本来、これまでの人類の歴史における最高到達点を指す言葉です。それを「今日の晩ご飯」のような日常的かつ一時的な体験に用いることで、言葉の価値が軽くなったように感じる人もいます。








































