
(前回:「文禄の役」だけでなく「慶長の役」も実は勝ち戦だった)
『誤解だらけの韓国史の真実 改訂新版』(清談社、5月4日発売)の刊行を機にした、日韓関係史の基礎知識の第6回である。
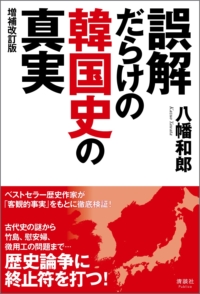
今日のテーマは新羅に関する話である。今回の著書では、韓国の歴代王朝の詳細な系図を掲載している。同等の情報密度を持つ系図を、手頃な価格の書籍で見ることはほとんどなく、それに限らず、本書は韓国史の初学者にとって教科書として利用できるよう、多くの工夫を施した内容となっている。
本記事で掲げている新羅王家の系図は、新羅建国から朝鮮半島を統一するまでの期間を対象としたものである。
新羅は、神功皇太后の遠征以降、日本と対立関係にあることが多かった国であり、百済が日本に友好的であったのとは対照的である。しかし、『三国史記』には、新羅の建国に日本人が深く関与していた旨が記されており、日本神話でも、主に出雲との関係において新羅との交流の深さをうかがい知ることができる。
「国引き神話」は、奈良時代に編纂された『出雲風土記』に記されている。それによれば、「この出雲の国は細長い布のように小さな国である。どこかの国を縫いつけて大きくしよう」と考えた神が、海の向こうを見渡して朝鮮半島の新羅に余った土地があるのを見つけ、大きな鋤を使って魚を突くようにその土地に打ち込み、丈夫な綱をかけて「国来、国来(くにこ、くにこ)」と言いながら引き寄せたところ、土地は船のようにゆっくりと動いて出雲の国にくっついたという。それが現在の出雲大社に近い杵築の岬であるという。
『日本書紀』では「一書に曰く」という程度の参考扱いであるが、スサノオノミコトがまず新羅に天降り、その後出雲に来たという記述も見られる。出雲と新羅は日本海を挟んで向かい合っているため、両者の関係が深いのは当然である。ただし、新羅のほうが先に栄えており、そこから文明が日本海側に伝えられたとする根拠は、まったく存在しない。










































