子供の頃にADHD(注意欠如・多動症)と診断された人は、大人になってからファストフードを頻繁に食べるようになる。
そうした関連性が米セント・ルイス大学(SLU)の最新研究で明らかになりました。
ADHDに関する研究は、学業や対人関係への影響が注目されがちですが、この研究では長期的な健康行動との関連に焦点を当てています。
なぜADHDの人は、ファストフードをよく食べるようになるのでしょうか?
研究の詳細は2024年12月25日付で医学雑誌『Journal of Attention Disorders』に掲載されました。
目次
- ADHDと診断されると、ファストフードの消費量が増加
- なぜファストフードを頻繁に食べるようになるのか?
ADHDと診断されると、ファストフードの消費量が増加
ADHDは、不安定な集中力や落ち着きのなさ、思いつきで行動してしまう衝動性などを特徴とする発達障害の一つです。
その多くは12歳以前の小児期に発覚することが多いですが、大人になってからでもADHDと診断される人は少なくありません。
ADHDについては常に多くの研究がなされており、これまでの研究では、ADHDのある子供が学校での集中力に欠けたり、対人関係でトラブルを起こしやすいことが知られていました。
その一方で、小児期に診断されたADHDが「運動」や「食習慣」といった長期的な健康行動に及ぼす影響についてはあまり明らかになっていません。
そこで研究チームは今回、ADHDと診断された子供が成人後に、どのような食習慣・運動習慣にあるかを調査しました。
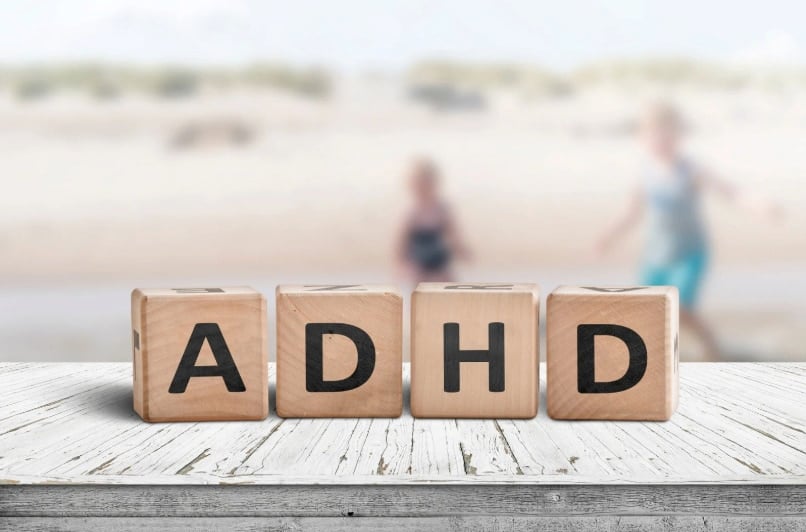
研究者らは、アメリカの青少年を長期間にわたって追跡した大規模な全国調査から、6814人のデータを使用しました。
ADHDの症状については、参加者が成人初期に達した段階で、自身の5歳から12歳までの行動を回顧的に報告することで評価されています。







































