更科功『世界一シンプルな進化論講義 生命・ヒト・生物――進化をめぐる6つの問い』は、生物進化の基本から最新の研究成果までを、わかりやすく解説した一般向けの講義形式の一冊である。著者は、進化を単なる「進歩」と捉える誤解を正し、「なぜ生物は変わるのか?」という根本的な問いに科学的に迫っている。取り上げられるキーワードは、「種の起源」「自然淘汰」「遺伝子」「生物」「生命現象」「ヒト」などであり、それらを軸にして、進化の仕組みや生物多様性の成り立ちを論じている。
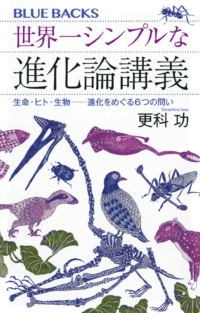
本書の大きな特徴の一つは、ダーウィンに対する立場の取り方である。著者はダーウィンを「歴史上もっとも偉大な生物学者」と位置づけながらも、その主張がすべて正しいとは考えていない。実際、ダーウィンの進化論には多数の誤りが含まれており、それを隠さず明確に指摘している。多くの類書がダーウィンを過度に崇拝するあまり、批判に対して歯切れの悪い表現にとどまっているのに対し、本書ではその点を率直に指摘している。

shalamov/iStock
本書では、進化論の内容について、ダーウィンの主張を6つに整理して説明している。
生物は進化する 自然淘汰が進化の主なメカニズムである 用不用説(使う器官は発達し、使わない器官は退化する) 生物は枝分かれ的に進化する 生物はゆっくり(漸進的に)進化する 進化は進歩ではない
これらのうち、1と4は当時から広く受け入れられたが、2の自然淘汰説は初期には否定的に捉えられ、著名な生物学者たちも懐疑的だった。
むしろ、自然淘汰説を積極的に支持したのは、ダーウィンではなく、アルフレッド・ラッセル・ウォレスやアウグスト・ヴァイスマンといった少数の学者であった。彼らが唱えた説は「ネオダーウィニズム」と呼ばれ、用不用説を否定し、自然淘汰を強調した内容だった。
その後、進化論は一時的に信頼を失い、20世紀初頭には「ダーウィニズムは死んだ」とまで言われた。だが、1930~40年代にかけて、ロナルド・フィッシャーやJ・B・S・ホールデン、シューアル・ライトらによって「集団遺伝学」という新たな学問分野が誕生し、進化を「遺伝子頻度の変化」として定量的に捉えることが可能となった。これにより、メンデル遺伝や突然変異の知見と自然淘汰を統合した「進化の総合説」が成立し、自然淘汰説は再び進化の中心理論として復権した。この理論は「ネオダーウィニズム」とも呼ばれているが、ダーウィン自身の考えが「ダーウィニズム」「ネオダーウィニズム」と呼ばれたことはない。












































