こうした遺伝子や形態的な類似は、地上や水中、森林など、多岐にわたる環境に適応してきたこれら3グループが、実は同じ“脱皮”という進化的履歴を共有する仲間であることを示すものです。
極限環境に強いクマムシ、粘着液を射出して獲物を捕らえるオンシフォラ、そして昆虫や甲殻類など膨大なバリエーションを誇る節足動物は、ぱっと見ではかなり異なるように思えますが、こうして共通の祖先から分かれた証拠を並べると、それぞれの多様性が深まった進化の軌跡がよりドラマチックに感じられます。
脱皮仲間の中でも異端児?クマムシを“最強”たらしめる理由
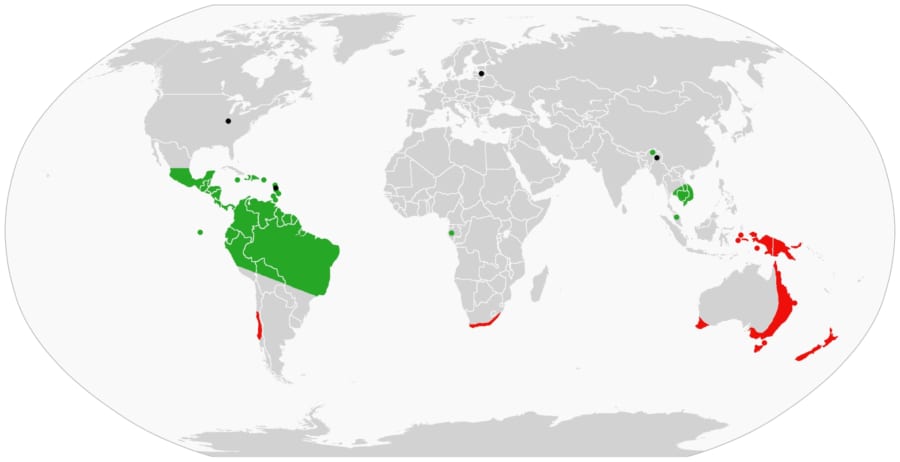
同じ脱皮動物(エクディソゾア)に属する中でも、クマムシ(緩歩動物)はとりわけ異色の存在かもしれません。
その最大の要因は、地球上でもっとも過酷とされる環境——極低温から極高温、乾燥、さらには宇宙空間の真空や高放射線下まで——を乗り越えられるという“最強”とも呼べる耐久性です。
その中心となるのが、「クリプトバイオシス」と呼ばれる特殊な生存戦略。乾燥などの強いストレスに直面すると、クマムシは体の水分をほぼ失う休眠状態に入り、代謝を極限まで低下させることで細胞やDNAを保護します。
この驚異的な耐久性を支えるメカニズムとしては、DNA損傷を抑えると推測されるDsup(Damage suppression protein)などのタンパク質が知られているものの、最近の研究では複数の保護機構が組み合わさっている可能性が高いことも示唆されています。
また、クマムシの中でも種によって耐久性のレベルや戦略には差があり、実はまだ謎も多い存在です。とはいえ、“宇宙空間でも生き延びた”という実験結果は、クマムシを有名にした大きな決め手となりました。
一方、脱皮仲間であるオンシフォラや節足動物は、脱皮を行うという点ではクマムシと共通していますが、極限環境での耐久力はあまり持ち合わせていません。












































