倉本圭造『論破という病 「分断の時代」の日本人の使命』 (中公新書ラクレ)は、日本社会の議論のあり方を見直し、「論破という病」を乗り越えて建設的な対話を実現する方法を探る意欲的な試みだ。著者は、過去20年間の日本では現実的な議論が成立しにくい状況が続いていたと指摘し、それを乗り越えることで、新たな時代の議論のスタイルが生まれると提言する。その視点は、まさに今求められているものではないだろうか。
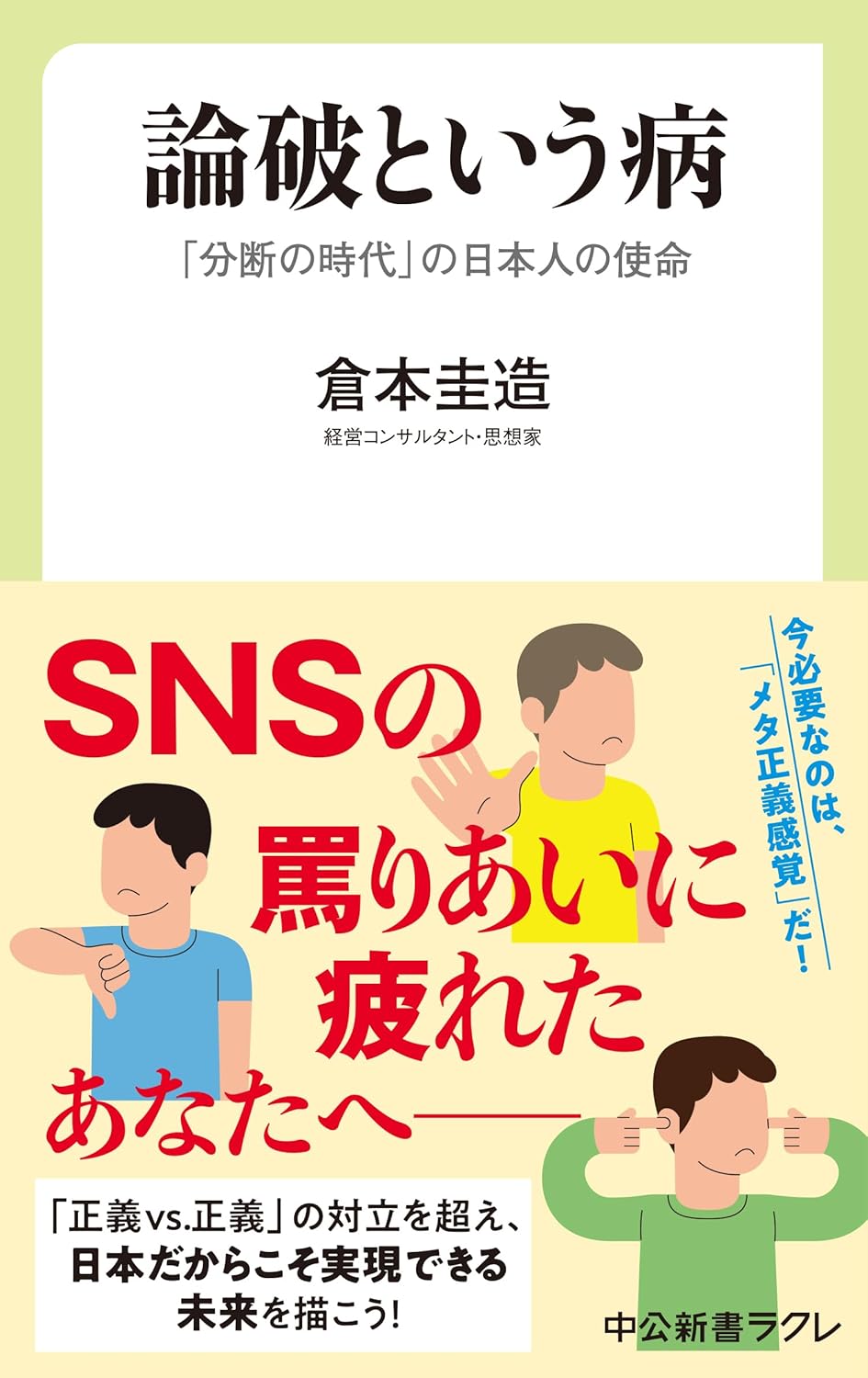 論破という病 「分断の時代」の日本人の使命
論破という病 「分断の時代」の日本人の使命
本書の核となる概念が「メタ正義感覚」だ。これは、相手の主張をそのまま受け入れるのではなく、その背後にある「正義の存在意義」を理解し、尊重しながら対話を進めるというものだ。単なる妥協ではなく、双方の意見を深掘りしながら、より良い「第三の道」を模索することの重要性が強調されている。このアプローチは、家庭の会話から企業経営、さらには社会全体の議論にまで応用可能であり、実践的な視点が随所に盛り込まれている。

recep-bg/iStock
例えば、家族旅行の行き先を決める場面が考えられる。沖縄旅行を提案する側と、それに反対する側の間で単に意見をぶつけるのではなく、「なぜ沖縄に行きたいのか?」という動機を深掘りすることで、新たな解決策が見えてくる。これは、個々の意見の背景にある価値観を理解しようとする姿勢が、より良い関係を築く上で不可欠であることを示唆している。
また、企業経営の例として、デジタル化を推進する経営側と、それに不安を感じる現場の従業員との間のギャップを、メタ正義感覚を用いて埋めることで、スムーズな移行が可能になったという。このように、本書は単なる理論書ではなく、実際にどのように活用できるのかを具体例を通じて示している点が魅力的だ。
さらに、社会全体の議論においても「メタ正義感覚」の有効性が論じられる。過去20年の日本では、「改革が必要だ」と主張する平成的な言論と、「現状を守るべきだ」とする昭和的な言論が対立し、前向きな解決策が生まれにくかったという指摘は非常に示唆に富む。しかし、この状況を「敵を論破して排除する」のではなく、相手の主張の背景にある正義を理解し、「どのようにすれば協力してより良い社会を作れるのか」を模索することこそが重要であると述べる本書のスタンスは、現代社会において新たな希望を示すものといえる。










































