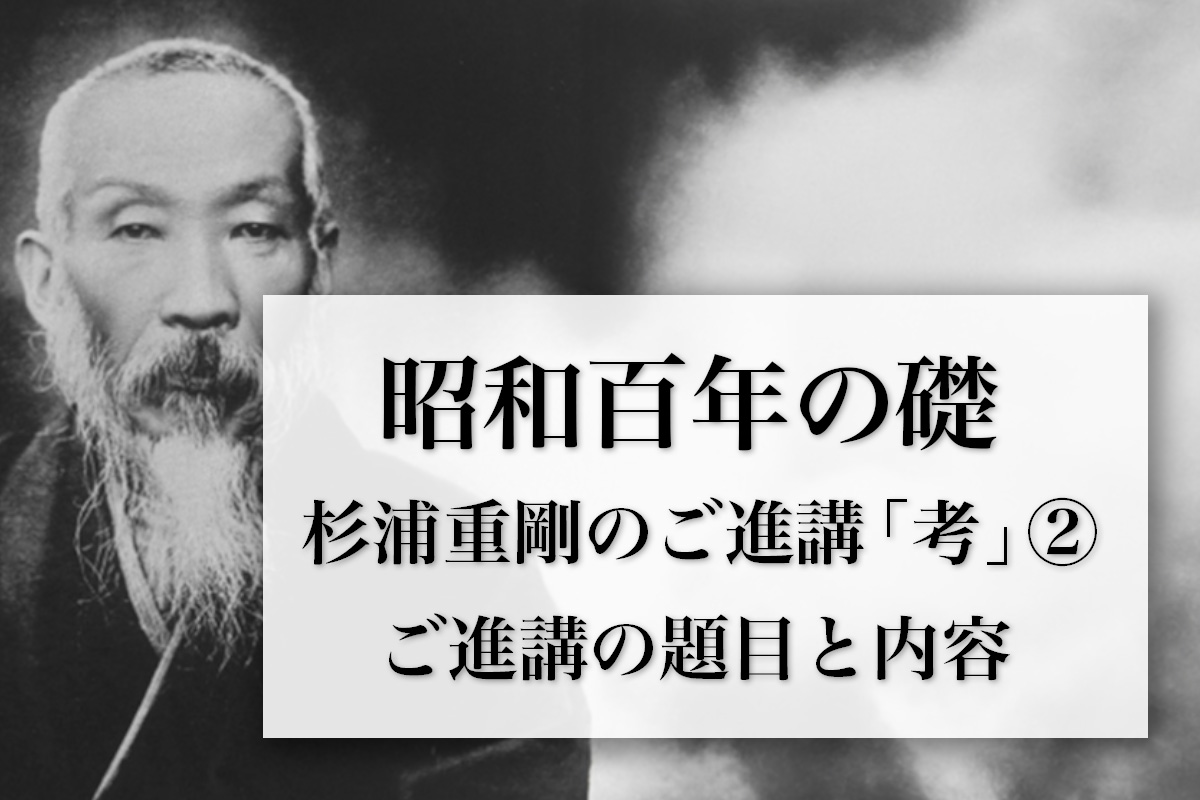
第一回目の進講は御用掛拝命からひと月余り経った1914年6月22日に行われた。題目は「三種の神器」であった。彼は次のように述べているが、拝命後に「生命を捧げて固より惜しむところがない」とも述べていた杉浦ならではの感想ではなかろうか。
(前回:昭和百年の礎①:杉浦重剛のご進講「考」)
今日第一回のご進講を申し上げた。昨日は医者に行って身体全部を診察してもらった。若し病気にでもなって今日の勤めを果たすことが出来なかったら、実に千秋の遺恨と思って注意した。今朝は先ず招魂社に参拝して、草稿を神前に供え、それから参殿してご進講申し上げた。丁度五分足らぬ位に講じ終わった。
進講当日の杉浦の日課は、午前3時起床、斎戒沐浴して暫し端座瞑想した後、一人静かに朝食をとり、6時に池袋の自宅から高輪の御学問所に人力車で向かう。7時に御用掛控室に入って心を落ち着け、殿下の登校を出迎えて、8時から進講を始めるというものであった。
杉浦は進講の眼目を、将来天皇となられる少年親王の人徳や見識を育成することに置いた。よって、基本方針を次の三点に置きつつも、その題目は古今東西の典籍は勿論のこと、偉人伝や花鳥風月や文物など森羅万象に及ぶという、趣向を凝らしたものだった。
一、 「三種の神器」に則り皇道を体し給うべきこと 二、 「五条の御誓文」を以て将来の標準と為し給うべきこと 三、 「教育勅語」の御主旨の貫徹を期し給うべきこと
進講草案の作成を補助した日本中学校教師(後に校長)の猪狩又蔵(史山)は1936年に『倫理御進講草案』(「原本」)を刊行した。それはB5版より少し大きい版の1180頁の大著で、定価12円(当時、米50kg相当)と高価ながら当時ベストセラーになった。が、収録されたのは御進講全281回のうち第1から第4学年までの153回分と第1学年後期の「教育勅語」11回分だけで、第5学年以降が欠けている。
1938年に「原本」を基に『倫理御進講草案抄』として「21題目の抄出本(120頁)」、「44題目の抄出本(353頁)」、「58項目の抄出本(500頁)」の三冊が出版された。本稿参考文献に掲げた『昭和天皇の学ばれた「倫理」御進講草案抄』は、この「44題目の抄出本」の再版である。筆者の住む横浜市の中央図書館に「原本」と「抄本」1冊が所蔵されているが、館内利用のみで貸し出しはされていない。








































