たとえば、学校内で市場シミュレーションや金融リテラシーを取り入れた実践型授業を導入することが考えられます。
第二に、教科書に書かれた方法にとらわれない、多様な計算戦略の提示と実践の機会が必要です。
市場で働く子どもたちが自ら発見した「分解」や「丸め」といった効率的な計算方法は、学校での固定的なアルゴリズムとは一線を画しています。
教育現場では、従来の一辺倒な計算方法だけでなく、直感的な解法や多様なアプローチを紹介し、生徒に実践させる機会を増やすべきです。
これにより、生徒たちは自分に合った方法を選び、柔軟に問題に対応できるようになるでしょう。
第三に、既存の教科書の型を破る早期の教育介入が重要です。
研究では、一度形成された思考の枠組みは後から変えにくいことが示唆されています。
したがって、幼少期や初等教育段階から、具体的な事例と抽象的なアプローチの両方を統合した指導を行うことが、将来の柔軟な数学的思考力の育成に不可欠です。
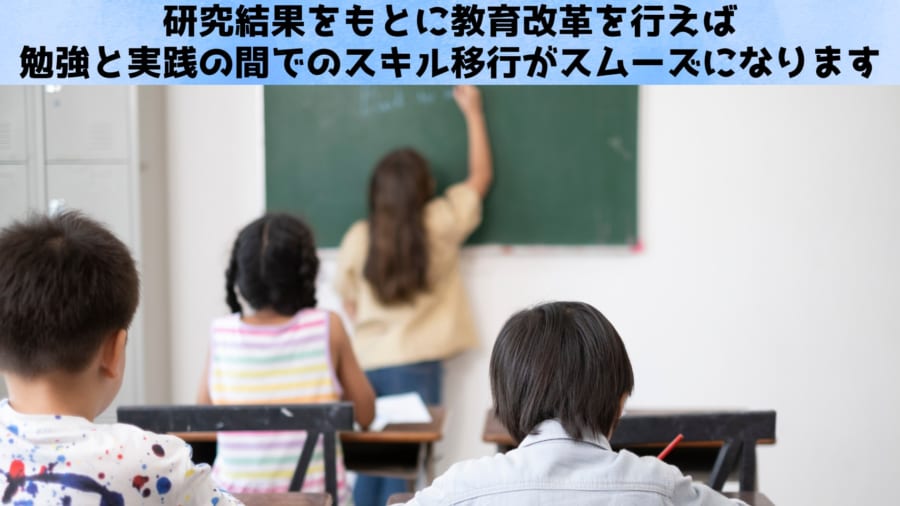
現在の日本では、教科書に縛られた教育が主流であり、教科書にない方法で問題を解くと周囲から「奇異」の目で見られることもあります。
(※実際、昭和時代に小学校に通っていた筆者は、教科書にない方法で問題を解いたために教師の逆鱗に触れ、教室の外に出される経験をしたことがあります。)
そのような風土を改善することは、日本の子供たちの計算能力を改善するのに役立つでしょう。
ノーベル経済学賞を受賞したエスター・デュフロ氏は、本研究について「学校で習う抽象的な数学と、現実の市場で実践される直感的な計算力は、実は全く異なるスキルセットです。
教室で鍛えられたアルゴリズムが、日常の複雑な取引にそのまま活かされるとは限りません」とコメントしています。
氏は、教育現場での指導方法において実生活との結びつきを強化する必要性を強調し、子どもたちが早期から具体的な事例に触れる機会を増やすことが、将来の柔軟な数学的思考の育成につながると述べています。




































