この「不思議な第六感」を解明しようとする試みは、化学や分子生物学、物理学など多方面の学術分野を巻き込みながら発展してきました。
一方、人類は近年、量子物理学の進歩を背景に超高感度な「量子マグネトメーター」を続々と開発しています。
量子センサーの世界では、磁気を測定する精度には「量子限界」という理論的な壁が存在することが広く知られています。
先にも述べたように、量子限界はどんなに精密に測定しても残ってしまう“揺らぎ”に起因するため、それを超えるセンサーは開発できません。
そのためもし鳥類の磁気感覚が量子的な効果を利用する生体量子センサーとして機能している場合、鳥類の磁気を検知する能力は量子限界で行き詰まりになるはずです。
そこで今回、クレタ大学の研究者たちは鳥類の磁気感覚を新たな手法で評価することにしました。
鳥類の磁気感覚は量子限界に達している
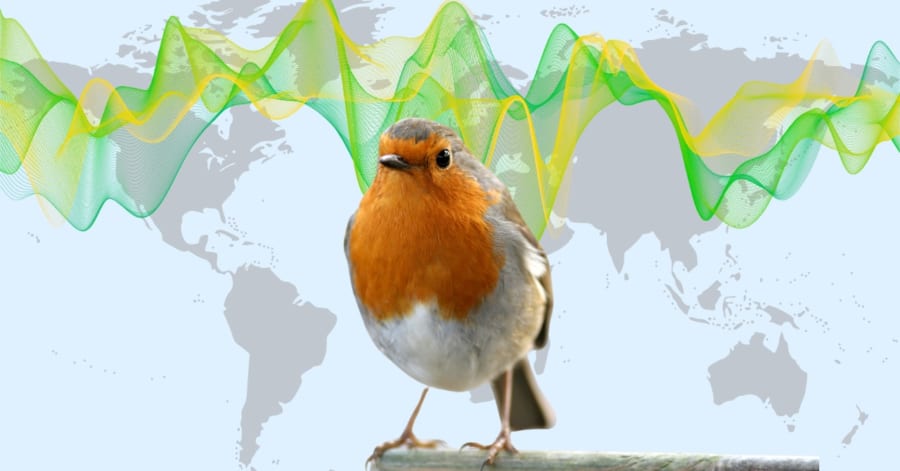
鳥類の磁気感覚は量子限界に達するほどの性能なのか。
謎を解明するため研究者たちは、「エネルギー分解能限界(ERL: energy resolution limit)」という指標を用いました。
ERLは、センサーが磁場を測定するときの基本的なパラメータであり、理論的にどの程度の精度が実現可能かを示す概念です。
ここでいう「センサー」とは人工の機械だけでなく、動物の体内にある分子や組織も含まれます。
そして研究者たちは、鳥類の磁場を感じ取るために使用すると考えられている、いくつかのメカニズムに対して、エネルギー分解能限界を用いた評価を行いました。
まず1番目に注目されたのが、ラジカル対機構(Radical-pair)です。
これは、網膜などに存在するクリプトクロム(タンパク質)の中で生じる「ラジカル対」という特別な電子状態が、地球磁場によって化学反応の割合をわずかに変化させる仕組みです。














































