近年はApple Musicに代表される「ハイレゾ音源」に対応するストリーミングサービスが登場しており、「CDより音質が良いサブスク」が珍しいものではなくなりつつあります。
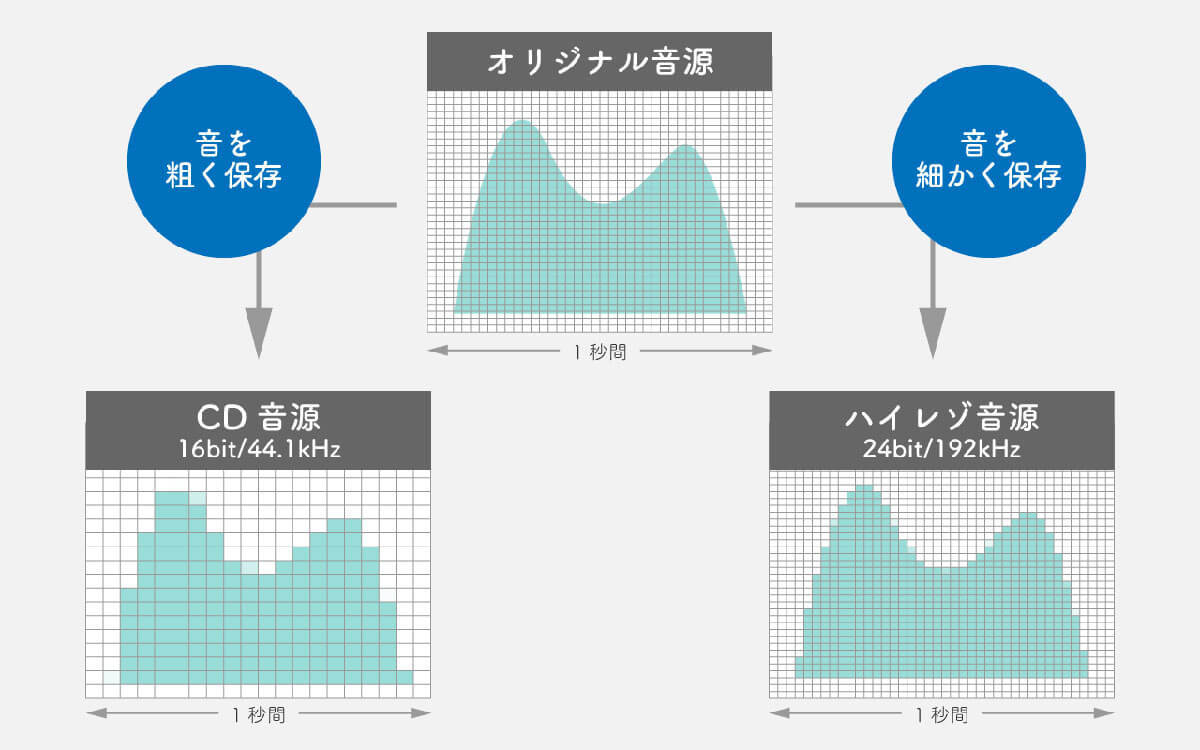
とはいえ、よく考えると、CDが製品化されたのは1980年代初頭のこと。約40年にわたり、CDが音楽再生媒体として汎用性と音質の両面で一線級のものであり続けているのはすさまじいことではないでしょうか。
ではそんなCDには、この40年の間に「ほかの媒体が主流になるピンチ」はなかったのでしょうか? 実は90年代末~00年代にはCDよりさらに高音質な「SACD」が登場しています。

SACDは、ソニーとフィリップスが1999年に開発した高音質オーディオディスク規格。CDよりも高い周波数帯域と量子化ビット数を使用し、DSD方式で音声を記録します。通常のCDと同じ大きさですが、最大100kHzを超える広帯域と120dB以上のダイナミックレンジを実現し、原音により忠実な再現を可能にしたものでした。
実は2024年現在でも生産が継続しているSACD。とはいえ、CDよりもはるかにマイナーだと感じる人が多いのではないでしょうか。ではなぜSACDは流行らなかったのでしょうか。3つの要因を解説します。
安価な再生機器が市場に登場するまでに時間を要した
1999年3月にソニーとフィリップスにより規格化されたSACDにとって、普及価格のコンポとして期待された存在が2003年発売のミニコンポ「Listen」シリーズでした。
「Listen」シリーズの最大の特徴はSACDの再生に対応していたこと。このシリーズは、音にこだわりのあるユーザー、主に大人をターゲットにしており、音質やデザイン面で高級志向のコンポないしはマイクロコンポとして展開。音質面では、高音域の再現性を高めるためにナノファイントゥイーターを採用し、低音域ではツインウーファーを搭載することで迫力のあるサウンドを実現していました。
とはいえ安価な再生機器が市場に登場するまでに約4年の月日を要したのは「長かった」側面がありました。00年代に入ると、たとえば初代iPodが2001年に登場するなど音楽の聴取環境自体に変化が起き始めていました。
CDは約40年間主流の音楽媒体であったことからも分かる通り、必ずしも低音質の媒体ではありません。「CDよりも音質が良い」という訴求は、初代iPodの登場などを背景によりインスタントに音楽を楽しむ動きが広がっていた時代にそぐわなかった側面がありそうです。
着うたが爆発的な人気を獲得した

2002年に「着うた」、2004年に「着うたフル」が開始されると大きなブームになり、総務省の「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する別添 調査結果(平成24年)」によると、ピークの2009年には市場規模1,201億円も記録しました。着うた、着うたフルの普及により、「携帯電話で音楽を聴くこと」が普通になっていき、それがのちにスマホでの音楽サブスクサービスを利用することに繋がっていきます。
つまり着うたフルはCDのようにコンポにディスクを挿入する必要もなく、iPodのように「iTunes Storeで購入した楽曲を端末に転送する」手間もなく、携帯電話で完結する音楽の楽しみ方として爆発的に普及したといえます。
「高音質」を謳うSACDが普及価格のコンポが出てもなお苦戦していた00年代前半に爆発的に市場が拡大したのは「着うた」だったというのは、ある種示唆的です。
先にも述べた通り、CDの音質が十分で「CD以上の高音質を求めている人はあまりいない」「もうちょっと簡単に音楽が聴けるほうが嬉しい」というのが当時の市場のニーズだったと考えられます。






































