本書『教養としての文明論』は、與那覇潤氏が呉座勇一氏に「文明論の復権」の意義について問いかけるところから始まります。呉座氏は『応仁の乱』の著者として「実証史学ブームの立役者」として知られていますが、呉座氏自身はその評価に違和感をもっていたそうです。実際には、初期の著作『一揆の原理』や『戦争の日本中世史』では、大きな歴史の見取り図を示すことを意識しており、日本史学界の細分化に対する異議申し立てを行ってきました。
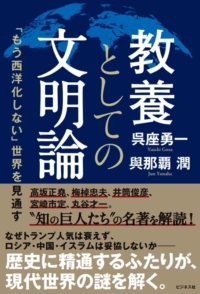
教養としての文明論
呉座氏は、現代の歴史学が細分化しすぎて一般の読者に伝わりにくくなっていることを憂慮しています。歴史を学ぶ意義が社会に届かない現状を打破するためにも、「文明論」の復権が必要であるという問題意識を提示しています。
ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』や「人新世」など、大きなスケールで歴史を捉える視点が注目を集めていることを挙げ、文明史の意義を強調します。

たとえば、梅棹忠夫の『文明の生態史観』を通じて文明という視点で歴史を考える意義について議論をしています。梅棹の指摘として、エジプトの知識人が自らをヨーロッパ人と認識する例を挙げ、文明という単位で歴史を捉えることで、国という自明性を相対化でき、国という枠組みを超えた多角的な歴史観が得られます。
『文明の生態史観』はその意義を示す好例であり、グローバルな歴史理解の重要性を再認識させるものです。ヨーロッパは近代化する際に、古典としてのギリシア・ローマの政治思想を参照し、自らをその後継者と位置づけましたが、それは自己イメージに過ぎません。一方で、「日本文明」という言い方を「日本は唯一無二で偉大だ」とする主張も最近はよく見られます。こういった自己中心的な自己認識を避けるためにも文明としての視点が重要です。



































