昨年10月以降のガザ危機は、世界を震撼させている。人的・物理的被害の度合いが深刻な甚だしい。しかもその衝撃は、思想部分にまで及んでいる。
日々の悲惨な出来事に沈痛な気持ちになりながら、なんとかそれでも鳥瞰的な視点を取り戻すために、私は、エドワード・サイード『オリエンタリズム』が無性に読みたくなった。言うまでもなく、パレスチナ系アメリカ人のコロンビア大学教授が1978年に出版した超有名な書籍である(邦訳は1986年)。
欧米人の「オリエンタル」なものに関する言説に根強く存在する偏見が、植民地主義的・帝国主義的な野望の隠れた正当化として作用してきたと主張した。いわゆる「ポスト・コロニアル」理論を確立した古典として知られる。
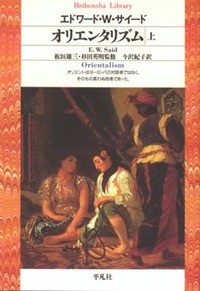
私は1987年に早稲田大学に入学した。当時はまだ国際政治学者になることなど想像していなかったが、何となく議論好きが集まるサークルには出入りし、学部ゼミは政治思想を専攻した。
1980年代末は、「ポスト・モダン」と呼ばれていた主にフランス系のポスト構造主義の思想が大流行していた。ジル・ドゥルーズやジャック・デリダの影響が強い浅田彰『構造と力』が1983年、レヴィ=ストロースの影響の強い中沢新一『チベットのモーツァルト』が1984年に出版されてベストセラーになった時代だ。大学生の間では柄谷行人や蓮見重彦が尊敬されていた。
サイードの『オリエンタリズム』は、英米圏で同時期に一世を風靡していた思想書だったので、大学入学してすぐにそのサイードの名前と「オリエンタリズム」の概念は、大学生の私にとっても必須知識の一つとなった。
しかしアメリカの現代思想というのは、正直、あまり先進的だとは思われていなかった。同じニューヨークの知識人でも、ドイツ出身の亡命ユダヤ人で『全体主義の起源』や『イェルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』で知られるハンナ・アーレントのほうが圧倒的に有名であったと思う。
しかし私は1993年からロンドンのLondon School of Economics and Political Science(LSE)の国際関係学部の博士課程に留学するが、そこで社会科学系分野で思想系の議論をしている教員や学生たちにとっては、サイードの存在が極めて大きいことに気づいた。
LSEは欧州の社会科学系分野の大学では1位にランクされる大学であり、世界各国から多様な知的土壌を持つ学生が集まっており、国際関係学部でも現代思想の議論が常に行われていた。やはりコロンビア大学にいたガヤトリ・スピヴァクの『サバルタンは語ることができるか』(原書は1988年、邦訳は1998年の出版)は共通知識の古典的な位置づけを獲得しており、頻繁に参照されていた。今日「ポスト・コロニアル」研究として確立された分野として認知されている思潮は、当時のLSEではすでにかなりはっきりと影響力を持っていた。
私は、LSEでの議論についていくためサイードやスピヴァックは、大量の文献の中の必読書として読んだのだが、正直、自分のPh.D.論文に使用するほどではなく、教養書のような位置づけで読んだだけだった。



































