目次
由来が古代中国まで遡る類義語
・風樹の嘆
・「風樹の嘆」の由来
まとめ
由来が古代中国まで遡る類義語
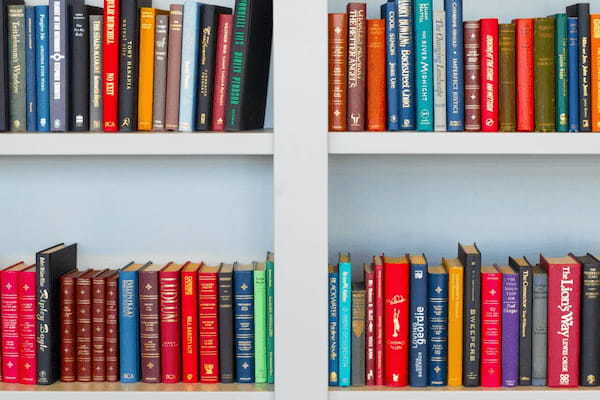
「石に布団は着せられず」の類義語のなかには、その由来が古代中国まで遡る類義語があります。
それが「風樹の嘆」です。
風樹の嘆
「風樹の嘆」は、父母がこの世になく親孝行できないこと、そしてそれを嘆くことを意味します。
「風樹」は風に吹かれて揺れ動く樹木のことをあらわしています。
樹木が静かにしていたいと願っていても、風が吹きやまなければ揺れ動き続けることになります。
これを、子供が親孝行したいと願った時にすでに親が亡くなっており叶うことのない願いに嘆いている様子と掛け、どうすることもできない状況を例えています。
「風樹の嘆」の由来
この「風樹の嘆」という言葉は、古代中国にまとめられた詩経の解説書『韓詩外伝』に由来があります。
その一節に「樹静かならんと欲すれども風止まず。子養わんと欲すれども親待たず。往きて見るを得べからざる者は親なり」とあります。
これは「木が静かにしていたいと切望しても、風がやまないとどうすることもできない。そして、親孝行しようと子供が願っても親は待ってくれない。亡くなってしまえば親には二度と会えないものだ」という意味合いが込められています。
そこから、「風樹の嘆」は親孝行の教訓として使用されるようになりました。
まとめ
「石に布団は着せられず」は、親孝行は早めに行うべきという教訓となることわざです。
経済的なゆとりができたので、一緒に旅行に移行など親孝行しようと考えたった思った頃にはもう両親が亡くなっているということもあるでしょう。
その墓石に布団をかけてあげても親孝行にはなりません。
だからこそ、生きている間に親孝行すべきです。
その教訓となるのが「石に布団は着せられず」です。
提供元・FUNDO
【関連記事】
・【恐怖動画】車から雪を取り除いていたら・・・数秒後に信じられない悲劇が発生!
・これだ!子供の時から食べたかったのは!お店で見つけた“とあるものの皮”が話題に!
・【だまし絵みたいな画像】あなたはこの画像の動物の正体がわかりますか?
・【奇跡的動画】シロフクロウを撮ろうと待ち構えていたら、想像以上に凄い動画が撮れた!
・これは激オコですわぁ・・・帰宅すると、二階の窓から注がれていた恐怖の視線が話題に!






































