それに対してボスは、まるで哲学の門答のように生きる意味や社会の仕組みを交えて若い二人に優しく語りかける。そして、究極的には贈与が次世代へと社会を継続させていく鍵であると結論付ける。
例えば、優斗は兄が返還義務のある奨学金について愚痴を言う兄を頭に思い浮かべる。若者への過大とも思える奨学金返済の経済的負担についてボスに意見を求めると、優斗の個人起点の見方に理解を示しつつも、社会全体の視点から返済することで次の人が奨学金を得る原資になっていることを説く。
奨学金を返済する個人と、その次に返済金を元手に新たに奨学金を得る個人が直接会う機会はない。しかし、奨学金を滞りなく返済するという行為が、本来は高等教育を受ける経済的余裕のない学生に対して学びの機会を保障している。この瞬間、お金は人と人を繋いでいるのである。
生活を支えるのはお金やと勘違いして、いつしかお金の奴隷に成り下がるんや。
元ゴールドマンサックス社員である著者の経歴を見ると意外にも思えるが、厳しい競争と苛烈なプレッシャーの中で16年間働いてきたからこそ見えてきた悟りの世界と言えるのかもしれない。
世の中を他人は信用できない激しい競争社会と捉えるか、お金を通じて有形無形に人は優しさという絆で繋がっていると感じられるのか。著者が提示する後者へと物の見方を転換できると、社会はとても温かく穏やかなで、まったく異なる景色に見えてくる。
■
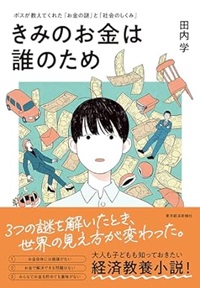
『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?










































