NHK番組が語る「進化」論への疑問
私はNHKの「ヒューマニエンス」という番組を毎回楽しく見ているのだが、多少気になるのは「進化」についてあまりにも楽観的というか目的論的に議論している点である。つまり、生物とか遺伝子に何か変化が起こると、何らかの目的を果たすのに便利なように「進化」した、みたいな論が多すぎる。しかし、生物学の教える進化の様相は、それほど単純ではない。
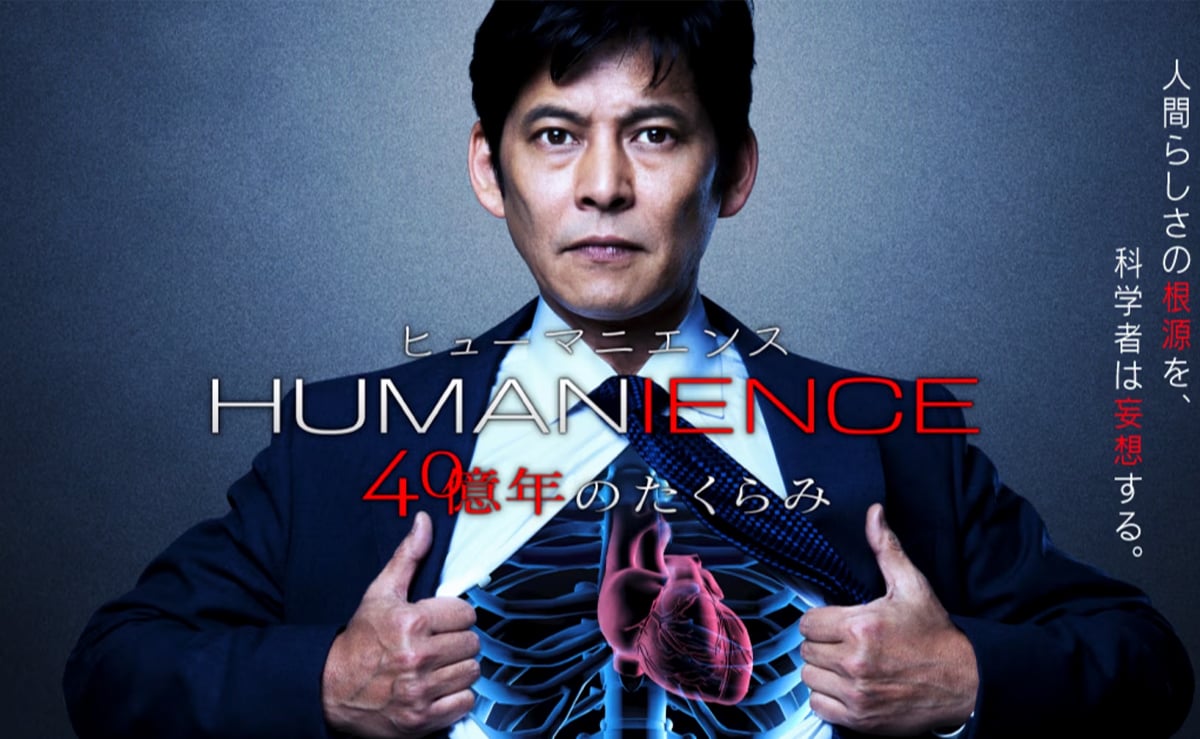
ヒューマニエンス NHKより
例えば生物「種」の概念は「掛け合わせて生まれた子が再び生殖できる範囲」である。例えば、人類は白人黒人何人であろうと混血児も生殖機能を持つから、すべて「ヒト科」の一種である。だから、人種差別は科学的に見ても明白に誤りである。
そもそも、全世界的に混血の進んだ現代において「純粋な○○人」など、未開民族等を除けば、ほぼ存在しないだろう。むろん「純粋な日本人」なども。分かっている範囲だけでも、日本人の起源は北方・南方系があり、縄文人と弥生人の混血もある。かつて、日本は「雑種文化」の国、と言った加藤周一の指摘は正しく、それは単に文化的な側面だけでなく、人類遺伝学的にも言えることである。
一方、ウマとロバの合いの子「ラバ」は生殖機能を欠くので「種」に数えられない。ヒョウとライオンの合いの子「レオポン」も同様だ。つまり「種」というのは結構「頑固」で、容易に入り混じったりしないのだ。だからこそ、長年にわたり同じ「種」が生息している。
生物「種」の多様性と進化の謎ところが、自然界には数百万以上の生物「種」がいる。最も多いのは昆虫で、哺乳類などは比較的少ないが、それでも6000種以上いる(広義の動物界の0.4%)。簡単に入り混じらないはずの「種」が、何故これ程までに多様に分化したのかが謎である。それに、同じ「種」の中でも外見だけでなく生態や機能が大きく異なるものがある。植物界も同様で、同じ「バラ科」の花が、如何に多様多彩であるかを見るだけでも、私などはその不思議さに打たれるばかりだ。
これらの多彩さに対する説明用語として「進化」が使われることが多いが、そのメカニズムは全然明らかでない。私の考えでは「進化」と言う概念は、変化を後から見て、後付けでつけた知恵のように思える。そもそも、親から子が生まれて行く過程の、どこで何が変化することによって、後から「進化」と呼ばれるほどの変化が起きるのか、全然分かっていない。
例えばヒトで言えば、樹上生活中心の四足歩行から地上に降りて直立歩行し、脳体積が拡大して行く過程を「進化」と呼んでいるが、その過程が「ひとりでに」自然に起こるとは、とても考えられない。また、このような変化は、なぜ一方向にしか進まないのだろうか?










































