
2023年10月上旬、キッコーマン取締役名誉会長の茂木友三郎氏らが設立した「令和国民会議」(通称「令和臨調」)が、財政・政策運営に関する提言「より良い未来を築く財政運営の実現に向けて―長期財政推計委員会と政策プログラム評価委員会の創設―」を取りまとめ、公表した。
提言にある「長期財政推計委員会」は、諸外国では「独立財政機関」(IFI:Independent Fiscal Institutions)と呼ばれるもので、財政運営に対する客観性を担保するために、予算編成のためのマクロ経済予測や財政パフォーマンスの監視、財政政策について規範的な助言や指針を政府に提供することを任務とする。
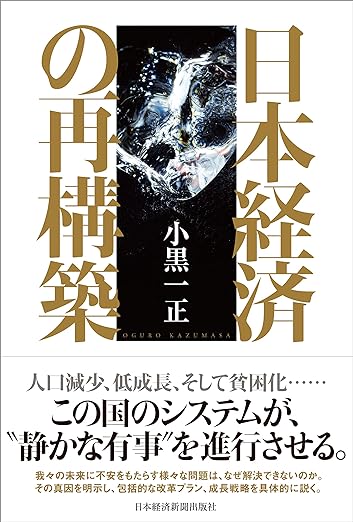
「独立財政機関」の創設は、拙著『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社・2020年初版)の第9章でも提言しており、東京財団のプロジェクトでも、林芳正・参議院議員(元外務大臣)らが「独立推計機関を国会に」という提言を行っているが、問題の本質が深まっているように思えない。
諸外国の独立財政機関では、より拘束力の強い中期財政フレーム、財政予測やリスクに関する包括的な報告書の作成、予算編成の前提となる指標の作成やルール順守を評価する試みなどを行っており、オランダの経済政策分析局(1945 年設立)やアメリカの議会予算局(CBO、1974 年設立)が長い歴史をもつ。
2000年以降では、例えば、イギリスの財政責任庁(OBR、2010年設立)のほか、スウェーデンの財政政策会議(2007年)、カナダの議会予算官(2008年)、アイルランドの財政諮問会議(2011年)など、OECD諸国で独立財政機関の設立が相次いでいる。
このため、日本でも独立財政機関を設置すべきとの提言や議論が盛り上がることは歓迎すべきだが、独立財政機関という組織が設置されたからといって、累増が進む日本の債務膨張にブレーキがかかるとは限らない。
なぜなら、現在も、内閣府は「経済財政諮問会議」で中長期試算を、また、財務省も「財政審」にて、(2018年に「起草検討委員提出資料」という形式で)長期財政推計を公表しているが、財政再建の動きが本格化している兆候は確認できないためだ。










































