座右の銘にされることもある「慎始敬終」。
手抜きをしないことを意味する四字熟語です。
慎むや敬うという漢字が含まれていますが、実際には慎みをあらわす言葉ではありません。
そこでここでは、この「慎始敬終」という四字熟語の意味や由来、用い方について解説します。
目次
「慎始敬終」とは
・「慎始敬終」の意味
・座右の銘としての「慎始敬終」
「慎始敬終」の成り立ち
・「慎」と「敬」のあらわすもの
・出典は古代中国でまとめられた『礼記』
「慎始敬終」とは
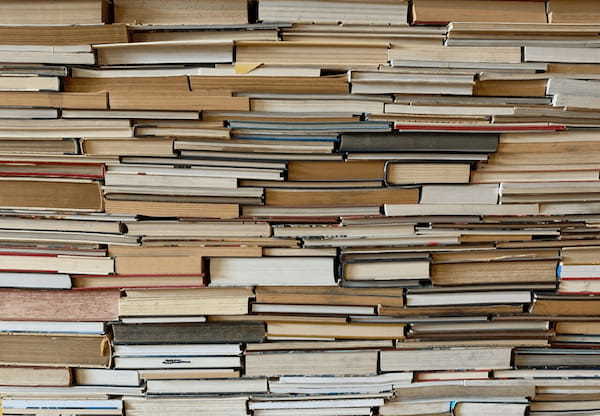
(画像=『FUNDO』より引用)
早速「慎始敬終」の意味について解説します。
「慎始敬終」の意味
「慎始敬終」は、最後まで気を抜くことなく手抜きすることもなくやり通すことを意味します。
ときに、物事は始めと終わりが肝心であるという戒めの意味で使用されることもあります。
座右の銘としての「慎始敬終」
「慎始敬終」は、座右の銘にされることもある四字熟語です。
その際は、仕事やプライベートにおいて何かに取り組むなら最後まで全力で臨むという心構えといった意味合いで用いられます。
「慎始敬終」の成り立ち
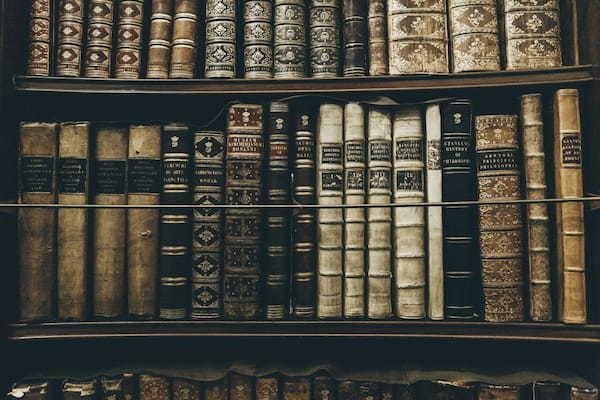
(画像=『FUNDO』より引用)
「慎始敬終」の成り立ちについて見ていきましょう。
慎と敬があらわすもの、そして出典について解説します。
「慎」と「敬」のあらわすもの
「慎始敬終」に「慎」と「敬」という漢字が含ま、れる事から、慎ましくあることを意味する言葉と思われる事もあります。
しかし、「慎始敬終」における「慎」と「敬」は、どちらも注意深く行動すること気をおろそかにしない事をあらわしています。
出典は古代中国でまとめられた『礼記』
「慎始敬終」は、古代中国でまとめられた『礼記-表記』にある「始めを慎み終わりを敬しむ」が出典となっています。
この『礼記』は全49篇ある儒教の経典で、前漢の時代にまとめられたものです。
君子の徳が民衆の規範となる事を論じた32篇『表記』に語源となる一節があります。









































