なるほど、米中間における「戦略レベルの安定性」は重要である。しかし、それが「かえってそれ以外のレベルの不安定性を惹起してしまう」。この「安定性・不安定性のパラドックス」という「逆説」は、台湾有事でも起こり得よう。
たとえば、以下のように。
……結局のところ、「安定性・不安定性のパラドックス」の問題は残り続けており、米国が中国との核エスカレーション回避に拘り続ける限り、例えば中国領内への本格的反抗のような、中国側の一線を越えると思われる台湾側の行動への支援には、引き続き躊躇せざるを得ないであろう……。
いかがであろうか。連日メディアが伝えるウクライナの惨状を思い出すまでもない。私には、そうした未来の悲惨な光景が、くっきりと目に浮かぶ。
昨年、ウクライナへの侵攻直前まで、アメリカは、積極的に機密情報(インテリジェンス)を公開し、「探知による抑止」を図った。この取り組みについても、前傾著で福田研究員はこう注意を促す。
確信的な現状変革の決意を固めた相手に対して、それだけでは有効でなかったと結論すべきである。状況把握の取り組みに加えて、物理的な対抗手段の手当なくしては、やはり侵攻の抑止そのものは図れなかったのである。
事実そのとおりであり、この点も、以下のとおり、台湾有事へのアナロジーが当てはまる。
ロシアのプーチン大統領であれ、中国の習近平主席であれ、確信的な現状変革の決意を固めた相手に対しては、「探知による抑止」だけでは効かない。物理的な対抗手段の手当なくしては、侵攻の抑止は図れない。
加えて、現在も続く経済制裁についても、福田研究員は「長期的には相手への強制手段として意味を持ち得るものの、短期的な足元の状況を左右する即効性はない」と指摘する。中国にも、きっと同じことが言えよう。先の「探知による抑止」に加え、これも重要な〝ウクライナの教訓〞ではないだろうか。
福田研究員は第2章をこう結ぶ。
以上のように、ウクライナ戦争の抑止破綻から得られる知見は、台湾海峡有事にも一定の含意を持つと考えられる。それらの含意が示すのは、ウクライナで抑止破綻を導いた要因は台湾海峡にも存在しており、実際に抑止の破綻が起こる可能性が無視できないということである。これを防ぐには、ウクライナでの抑止破綻の事例を教訓に、現状維持勢力としての抑止の強化に努めるほかないであろう。(中略)確信的な現状変革の意図を持つ相手に対しては、やはり物理的手段での対抗措置を採るほかないであろう。
なんら異論を覚えない。
■
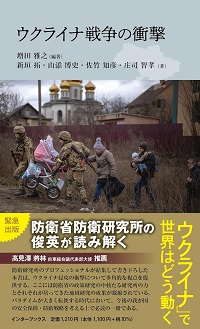
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?









































