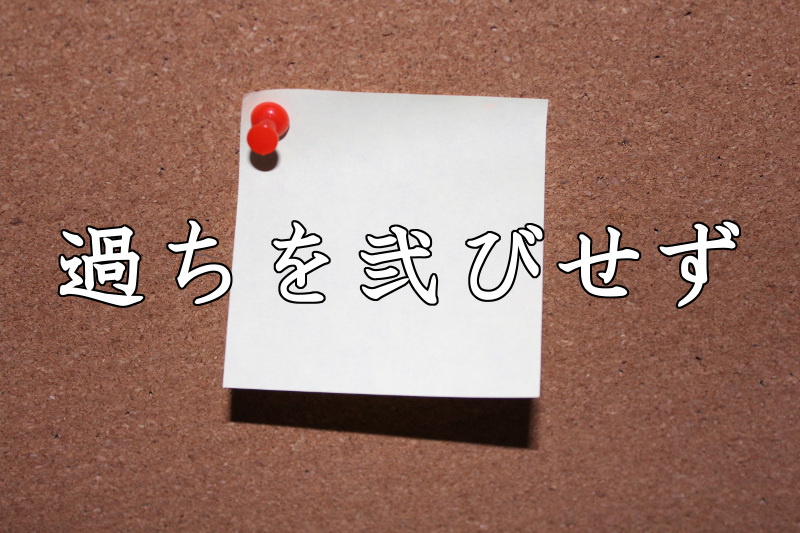
『論語』に、「過ちて改めざる、是(こ)れを過ちと謂(い)う」(衛霊公第十五の三十)とあります。人が自分の過ちに気付いたとして、何故「改めざる」のでしょうか。「正しさを認めたら負け」「痛い目に合いたくない。白を切ろう」--修養が足りないので、素直に過ちを認められず、悔い改められないのだと思います。心に見栄とか執着とかエゴといったものがあらわれ、結局過ちを繕うのだと思います。
私は常日頃、自分自身にも社員に対しても「過ちは過ちと認めて、過ちを二度と繰り返さないように」と言い聞かせています。何の間違いも犯さない神のような人間など此の世には存在せず、過つことは仕方がありません。但し、過った後の行動がどうなのかが問題なのです。「小人の過つや、必ず文(かざ)る」(子張第十九の八)というように、とかく小人は自分が過った場合それを素直に認めずに、人のせいにしたり、あれこれと言い訳をしたりするものです。更には、その過ち自体を正しいなどと言い触らし、人に押し付けて行くような愚人すらいます。
そうではなくて「君子は諸(これ)を己に求め」(衛霊公第十五の二十一)、繰り返し過たぬよう細心の注意を払うことが大事です。『易経』に、「君子豹変す、小人は面(おもて)を革(あらた)む…君子とは自己革新を図り、小人は表面だけは改めるが、本質的には何の変化もない」とあります。君子たる者「過てば則(すなわ)ち改むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ」(学而第一の八/子罕第九の二十五)、という姿勢を持たなければなりません。










































