だが、あまりにも割高に見える
ところが、先ほどご紹介したように奴隷の価格は住宅とほぼ同一として奴隷の価値を算出すると、もっと高額になってしまいます。
.png) こちらは最低でも15万ドル、最高では43万ドルとはるかに高くなっていますが、奴隷1人が住宅1戸という大ざっぱな価値観が正しいとすれば、奴隷所有者たちはずいぶん割高な水準でも奴隷を手放すことなく使いつづけていたと考えるべきなのでしょうか。
こちらは最低でも15万ドル、最高では43万ドルとはるかに高くなっていますが、奴隷1人が住宅1戸という大ざっぱな価値観が正しいとすれば、奴隷所有者たちはずいぶん割高な水準でも奴隷を手放すことなく使いつづけていたと考えるべきなのでしょうか。
現在までの奴隷制経済研究者たちのコンセンサスは「奴隷という高額商品を買えるというプレステージのもたらす有形無形の利益があるので、農園主たちは無理をしてでも高値の奴隷を買いつづけていた」ということになっているようです。
その背景として「奴隷が使えなくなると綿花価格が急上昇するとか、綿花生産量が激減するとかのマイナスがあるので、実際には奴隷価格は割高ではなかったのではないか」という仮説が、データを見るかぎり成立しないという認識があります。
まず価格ですが、奴隷を使えなくなった南北戦争以後も直後の混乱期以外は上昇どころか徐々に低下しています。
.png) さらに生産量を見ると、これも南北戦争中から直後にかけての一過性の落ちこみを除けば、順調に増加しつづけていました。
さらに生産量を見ると、これも南北戦争中から直後にかけての一過性の落ちこみを除けば、順調に増加しつづけていました。
.png) つまり、奴隷を使った綿花栽培には特有の利点があって、その利点が奴隷価格に反映されていたという仮説は却下されるわけです。
つまり、奴隷を使った綿花栽培には特有の利点があって、その利点が奴隷価格に反映されていたという仮説は却下されるわけです。
ということは、農園主たちはプレステージのために割高を承知で奴隷を高値で買っていたのでしょうか。
奴隷をひとりも持っていなかった農園主がなんとか資金を貯めてやっと1人か2人買ったというならわかりますが、数百人、数千人の奴隷所有者が、そんなに割高な資産を買い集めつづけるものでしょうか。大いに疑問です。
従来の奴隷制経済研究者たちは、奴隷の購入と機械への投資を比べるとき、重要な差を見落としてきたのではないでしょうか。
たとえば、現代奴隷制研究の第一人者と呼ばれているケヴィン・ベイルズは、次のように述べています。
.png) この引用を読むと、奴隷は子どもを産むことさえ禁じられていたかのような印象を受けます。奴隷社会史の研究者たちの見解はまったく違います。
この引用を読むと、奴隷は子どもを産むことさえ禁じられていたかのような印象を受けます。奴隷社会史の研究者たちの見解はまったく違います。
少なくとも男女数人以上の奴隷を持っている農園主にとって、奴隷を購入することの最大のうま味は減価償却費を積み立てて、耐用年限のきた機械の次にどんな機械を購入するか検討する必要がないことでした。
奴隷たち自身がマザーマシン、ファーザーマシンとなって次世代の奴隷を産んでくれるからです。
奴隷たちが育てた子どもたちは、もちろん農園主の所有物ですから、経営規模の拡大に使うこともできるし、奴隷市場で売ることもできます。綿花栽培からの収益より奴隷繁殖農家としての収益のほうが大きかった農園もそれほど珍しいことではなかったのです。
私は「利子産み資本」という会計用語自体が、最初はカリブ海島嶼国家でのサトウキビ栽培と搾汁経営に奴隷を使った人たちの実感がなければ誕生しなかったほど、奴隷が奴隷を産むことによる事業規模と収益の拡大への貢献度は高かったのだろうと思います。
実際、南北戦争が間近に迫った1840~50年代にアメリカの奴隷市場で売りに出されていた奴隷の大半は、海外から連れてこられた奴隷ではなく、アメリカ国内の奴隷制プランテーションで育った奴隷たちでした。
そして、奴隷の高度な利子産み資本性を考えれば、1世代の奴隷が自分の労働でどの程度農園全体の収益に貢献するかだけではなく、自分の子どもを産み育てる機械と見た場合の奴隷の価値はずっと大きくなっているので、奴隷価格は決して過大評価ではなかったと思います。
奴隷制には強力な権力装置が不可欠もうひとつ、アメリカで奴隷制綿花栽培が普及したことに伴う大きな社会的変化がありました。それは、強力な権力機構を構築しなければ社会全体が円滑に動かないということです。次の地図グラフをご覧ください。
.png) 数はそれほど多くありませんが、総人口5万人以上でそのうち95%以上が奴隷というコミュニティもあったのです。
数はそれほど多くありませんが、総人口5万人以上でそのうち95%以上が奴隷というコミュニティもあったのです。
こうなると、何かの理由で奴隷たちの憤懣が爆発すると、まず手元にかなり強力な銃砲が揃っていないと危険ですし、集団脱走を試みる奴隷たちを押しとどめるにも、それなりの武装が不可欠です。
アメリカでは現在でも保守派の人たちは「人民武装権」を守ることに大変熱心ですが、開拓時代からの、一握りの支配者が多くの奴隷たちを押さえつけなければ秩序が保てないという社会構造がもたらした恐怖心は、現代にいたるまで刷り込まれているのだと思います。
さらに、連邦政府や州政府の警察機構が迅速に対応してくれなければ、リンチもまた正当な「裁き」であるという考え方も、かなり最近まで根強く残っていました。
西欧一般に共通する「奴隷制なくして文明無し」論アメリカに限らず西欧諸国一般に、古典古代と呼ばれるギリシャ・ローマ文明が異常に奴隷制生産に対する依存度の高い文明だったという事実を、奴隷制無しに文明はあり得なかったという方向に解釈する傾向が顕著です。
ここで、19世紀半ばに生まれたアイルランド生まれのイギリス人で典型的な文科系のオスカー・ワイルドと、セルビア人で典型的な理科系の二コラ・テスラがまったく同じような文明観と未来への希望を語っていたという事実をご紹介しましょう。
.png)
このふたりは人間に奴隷労働をさせるのは非人間的だという点で比較的まっとうな世界観を持っていたと思います。ところが、奴隷制労働だけではなく、労働一般が奴隷労働であり、人類は労働から解放されなければならないと唱えた人がいました。
イギリス有数の大貴族の家に生まれ伯爵位を継いだバートランド・ラッセルがその人ですが、同時に哲学者、数学者、そして反戦平和運動の闘士として刑務所に拘留されたこともあった人です。人格者として尊敬するファンの多い人なのですが、じつはとんでもないエリート主義者でした。
第一次世界大戦直後の1923年に出版された『工業文明の展望』と、大不況が始まった1930年に出版された『科学的世界観』から、彼にとっての理想の社会を再構築してみましょう。
.png)
とにかく「優良な遺伝子を持ったエリートの血統を残し、そうでない一般大衆はほとんど何ひとつ生きる目的もなく時間を潰して死んでいくのが分相応であり、家族などという古めかしい紐帯は断ち切ってしまえ」と断言していることに驚きます。
さらに、露骨な人種差別的言辞は出てきませんが「アフリカを手放さないかぎり」西欧は第3勢力として生き延びることができるという主張から、「アフリカ人が独立したいと思うことなどあり得ない」と考えていたことがわかります。
100年なんの進歩もなかったアフリカ観この文章は今からちょうど100年前の1923年に刊行された本の一節ですが、100年経った今も西欧人の世界観はほとんど変わっていないなと考えさせられる事件が起きました。
マリ、ニジェール、ガボンとアフリカの旧フランス植民地各国でフランスと結託した腐敗政権を打倒する軍事クーデターが続きましたが、フランスのマクロン大統領が「フランスにアフリカの旧植民地を手放す気はない」と宣言したのです。
フランスはモロッコからソマリアにいたる植民地を獲得してアフリカ大陸を横断する政策でイギリスのエジプトから南アフリカへの縦断政策に対抗したのですが、スーダンのファショダという場所で両軍が激突し、結局フランスの敗北に終わったという経緯があります。
次の地図とグラフでおわかりいただけるように、スーダンは今もアフリカ大陸でいちばん多くのクーデターを経験し、旧フランス領諸国は2番手グループを形成しています。
.png)
フランス大革命が起きた18世紀末から20世紀初頭にいたる英仏両国のアフリカ大陸植民地争奪戦の余燼が、激発するクーデターとして続いてきたのです。
その中でフランスの旧フランス植民地諸国に対する政策は、かんたんに言えば独立は名ばかりで今でも植民地と見なしていることがはっきりわかる傲慢なものでした。
アフリカ植民地フランというフランスで印刷した通貨を押し付けて通貨発行益(シニョリージ)を奪い取りつづけ、ニジェールのウランのような重要天然資源はフランス国営企業が長期独占買い付け契約で市価よりはるかに安く買い叩きつづけてきたのです。
それだけ相手国を怒らせておきながら「アフリカにあるフランスの旧植民地は今でもフランスの所有物であり、手放すか、手放さないかはフランスが勝手に決めることだ」と言ってのけるからには、そうとうな覚悟があるのだろうと思っていました。
でも、この3ヵ国が外敵からの攻撃に備えて相互防衛協定を結んだとのニュースが流れただけで、あっさりニジェールの暫定軍事政権の要求通りに駐ニジェール大使を召還し、ニジェールに駐屯していた1500名のフランス軍兵士を今年末までに撤退させると言い出したのです。
そんなにあっさり折れるなら、始めから「手放す気はない」などと言わなければいいじゃないかと思いますが、この期に及んでもヨーロッパを中心に世界は回っていると思いこんでいたのでしょう。
アメリカにも100年の蹉跌がアメリカが抱える人種問題の深刻さは、南北戦争で敗れたことによって膨大な人数の高額「商品」、黒人奴隷を無償で開放しなければならなかった南部諸州だけではなく、北軍に参加して戦った北部諸州でも、白人集団による黒人のリンチが続いたことに表れています。
しかも、新聞にいつどこでと予告広告を出して、何千人もの観衆を集めて残虐きわまる処刑を実行し、記念絵葉書を印刷して売るほどコマーシャリズムも旺盛で、さらし者にした犠牲者の遺体の一部を観衆が奪い合うといったことすべてがお祭り騒ぎになっていたのです。
.png) そして、南部では「区別すれども差別なき平等」という偽善的なことばで、あからさまな差別待遇が延々と正当化されつづけていました。
そして、南部では「区別すれども差別なき平等」という偽善的なことばで、あからさまな差別待遇が延々と正当化されつづけていました。
.png)
1960年代に盛り上がった公民権運動は、黒人たちだけではなく良心的な白人学生たちの犠牲のもとに、表面的には露骨な人種差別を一掃しました。
.png)
もう深南部の田舎町に行っても、上の写真2枚のような光景にお目にかかることはないでしょう。
むしろ、民主党系でジョージ・ソロスの選挙資金で当選した市長や検事総長がいる自治体では、黒人やヒスパニックなどのマイノリティが犯した犯罪にはできるだけ寛容に対処する方針が目立つようになっています。
いまだに共和党を支持する保守派の人々の中には「アメリカの黒人にとって最良の日は先祖が奴隷商人に連れられてアメリカに来た日だ。それがなければ、今もアフリカの奥地で衣食もままならない日を過ごしていただろう」と言ってのける人もいます。
ただ、こういう人たちと犯罪者に優しくすればマイノリティ票を確保できると思っている人たちと、どちらがより深刻な人種差別主義者なのか、判断に迷います。
ソロス派の市長や検事総長は「マイノリティ一般が、刑罰さえ軽くて済むなら犯罪を犯したいと思っている連中だ」と考えているわけですから。
バートランド・ラッセルからちょうど100年後に、フランスのマクロン大統領が「フランスはアフリカを手放さない」と言ったのと同じように、アメリカ連邦議会に最初のリンチ禁止法が上程されてから100年以上経って、やっとリンチは連邦レベルでのヘイトクライムだとする法案が下院を通過しました。
.png)
奴隷制と文明とは不可分だとする伝統のある国々では、強い立場にある者が弱い立場の人々を、ときには生理的変更まで加えて自分たちに都合のいいようにつくり変えるという伝統も脈々と流れています。
古代ギリシャ・ローマの自由民と奴隷。大航海時代以来の宗主国と植民地先住民。南北戦争前アメリカの旦那方と黒人奴隷。そして現代の知的エリートと一般大衆。
イギリス優性学会会長を務め、国連ユネスコの創設者のひとりでもあったジュリアン・ハクスレーは「畜産農家ならどこでも家畜にやっていることを人間相手にやろうとすると大騒ぎになるのは、謎だ」と言いつづけてきたそうです。
ハクスレーやバートランド・ラッセルが夢見た優秀な遺伝子を持つ人間だけが子孫を残せる世界にならないことを祈ります。
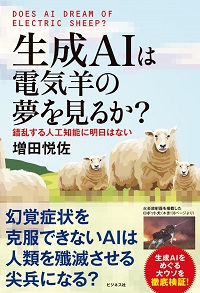 増田先生の新刊 生成AIは電気羊の夢を見るか? が好評発売中です。ぜひご覧ください。
増田先生の新刊 生成AIは電気羊の夢を見るか? が好評発売中です。ぜひご覧ください。
遊び道具としてならAIもおもしろく使えるが…… 米銀には10月こそいちばん残酷な月 生成AIの花形企業、エヌヴィディアに不正取引・粉飾決算疑惑浮上 開けてビックリ、好業績で割高さが再認識されたエヌヴィディア決算 アフリカ戦線異常あり 自動車自律走行はGREAT PIE IN THE SKY(バカでかい絵に描いた餅)

Donny DBM/iStock
編集部より:この記事は増田悦佐氏のブログ「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」2023年10月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」をご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?










































